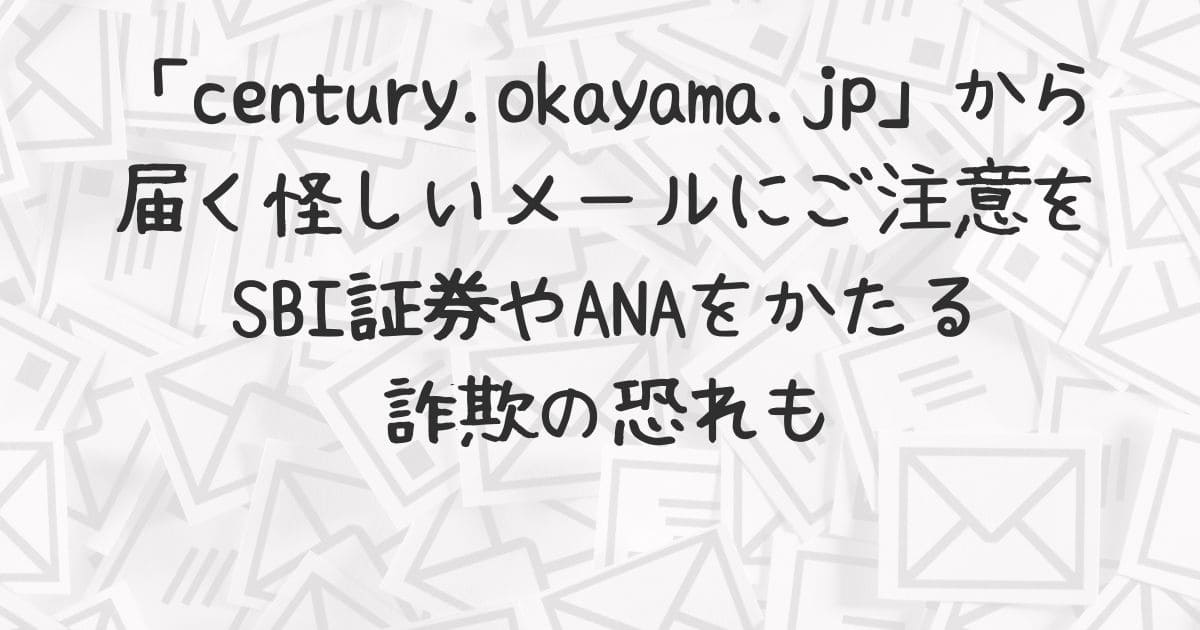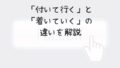最近、「century.okayama.jp」というドメインから送信された不審なメールを受け取ったという報告が相次いでいます。
受信者には注意が必要です。
メールの内容としては、たとえば【SBI証券】を名乗り、「セキュリティ強化のため、ただちにアカウントの設定を確認してください」といった、受信者の不安を煽る文言が使われています。
こうしたメールは、見た目は本物そっくりでも、実際には個人情報を盗み取ることを目的としたフィッシング詐欺の可能性があります。
本文中のリンクを安易にクリックしたり、氏名・ID・パスワードなどの個人情報を入力したりするのは大変危険です。
少しでも不審に感じた場合は、メールの内容を鵜呑みにせず、公式サイトや正規のサポート窓口を通じて確認するようにしましょう。
【注意喚起】「century.okayama.jp」からのメールにご注意を|SBI証券やANAを装った詐欺の手口とは?

最近、「century.okayama.jp」という送信元を使った不審なメールが確認されており、その中にはSBI証券や**ANA(全日本空輸)**を名乗る偽の案内が含まれています。
見た目は本物そっくりで、内容も巧妙に作られているため、思わず信じてしまうケースも少なくありません。
以下に、その具体的な事例と注意点をご紹介します。
事例①|SBI証券をかたる偽メールの内容
いつもSBI証券をご利用いただき、ありがとうございます。
現在、インターネットを介した不正アクセスの増加に伴い、当社ではセキュリティ強化を実施しております。
そのため、お客様にも新たなセキュリティ設定へのご協力をお願いしております。下記の期限までに、設定変更を完了いただきますようお願い申し上げます。
対応期限:2025年4月13日(土)
※期限を過ぎた場合、一部のアカウント機能に制限がかかる可能性があります。
▼セキュリティ設定ページ(※公式と記載された偽のリンク)
[リンク記載]安全な運用のため、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
このようなメールには、「個人宛ての重要なお知らせ」「無断転送禁止」といった一見本物らしい注意書きが添えられていますが、すべて偽装の可能性があります。
事例②|ANAマイレージクラブを騙るメール
ANAマイレージクラブをご利用いただき、ありがとうございます。
ご登録の情報と予約時の内容に相違があったため、一部のマイルが正常に加算されていないことを確認しました。
以下の内容をご確認いただき、マイルの手動加算手続きをお願いいたします。
未加算マイル:8,629マイル
対応期限:メール受信から24時間以内▼会員情報の確認・修正はこちら
「https://ana-co-jp.trainturk.com」
※リンクは受信後24時間以内のみ有効です。
このメールも非常に巧妙で、正規のANAから届いたように見えますが、URLが正規ドメインではない点に注目してください。
たとえば「trainturk.com」など、ANAとは無関係のドメインが使われています。
なぜ信じやすいのか?その仕組みと見破るポイント
こうしたフィッシングメールは、実在する企業の名称やそれらしいデザイン・表現を巧みに利用して、受信者を信じ込ませようとします。
見分けがつきにくい理由は、以下のような点にあります:
-
文面が丁寧で、公式メールのように整っている
-
差出人名や件名がもっともらしい
-
巧妙に作られた偽リンクを「公式サイト確認済み」と偽装している
被害に遭わないための3つの対処法
-
メール内のリンクは絶対にクリックしない
不審なメールでは、どんなに気になってもURLを開かないようにしましょう。 -
不安な場合は、公式サイトやサポートに直接確認を
企業からの連絡が本物かどうか不安な場合は、メールのリンクではなく、自分でブラウザを開いて公式サイトにアクセスし、そこで確認してください。 -
URLのドメインをよく見る
信頼できる企業のメールは、その会社の正規ドメイン(例:@sbisec.co.jp や @ana.co.jp)から送られます。不自然なドメインや見覚えのないURLが含まれている場合は、詐欺の可能性が高いです。
注意点まとめ
こうした詐欺メールは、どれほど警戒していても、思いがけず信じてしまうこともあります。
万が一、リンクをクリックしてしまったり、情報を入力してしまった場合は、すぐにパスワードを変更し、関係機関に相談してください。
【警戒を】「century.okayama.jp」から届く不審メールに要注意

迷惑メールを受け取ったときに取るべき正しい対応とは?
ある日突然、身に覚えのないメールが届くと、「何か大事な連絡かもしれない」と不安になることもあるでしょう。
しかし、その場で慌てて行動してしまうのは危険です。
まずは落ち着いて、冷静に内容を見極めることが大切です。
■ 絶対にリンクを開かない・添付ファイルを開かない!
迷惑メールの多くは、本文に記載されたリンクをクリックさせたり、添付されたファイルを開かせたりすることで、受信者から情報を引き出そうとします。
これによって以下のような被害が発生する恐れがあります:
-
偽のログインページに誘導され、IDやパスワード、クレジットカード情報などを入力させられる
-
ウイルスやスパイウェアに感染し、端末内のデータが盗まれる
-
アカウントが乗っ取られ、自分になりすました不正行為に使われる可能性がある
どんなに内容が気になっても、メール内のリンクやファイルには絶対に手を触れないようにしましょう。これが自分の情報を守る最初の防衛線です。
■ 返信しない・相手と連絡を取らないこと
「支払いが滞っています」「アカウントが停止されました」といった不安をあおる内容が記載されていると、思わず返信してしまいそうになりますが、それは大変危険です。
一度でも返信してしまうと、あなたのメールアドレスが“生きている”ことを相手に知られてしまい、さらに多くの迷惑メールの標的になる恐れがあります。
また、返信を通じて巧みに個人情報を引き出されるリスクもあるため、相手と一切の接触を避けることが重要です。
■ 差出人アドレスをしっかり確認しよう
迷惑メールかどうかを判断する上で、まずチェックすべきなのが差出人のメールアドレスです。
たとえば、Amazonや楽天などの大手企業からの連絡であれば、公式ドメイン(@amazon.co.jp など)が使われているはずです。
一見それらしく見えても、微妙に異なるドメインや不自然な文字列が含まれている場合は、偽装されたメールの可能性が高いといえます。
■ 日本語の不自然さにも注目
迷惑メールの多くは、翻訳ツールを使って作られているため、日本語の文章に違和感があることがよくあります。
-
文法的におかしい言い回し
-
丁寧語とタメ口が混ざっている
-
フォントや句読点の不統一
こうした不自然な表現を見かけたら、偽のメールを疑ってください。
■ 不安なときは公式サイトで直接確認を
メールの内容に少しでも疑問を感じたら、記載されているリンクを使わず、自分で公式サイトや正規のアプリからログインして確認を行いましょう。
たとえば、「アカウントがロックされた」というメールを受け取った場合は、Amazonや銀行などの正規サイトから直接アクセスして確認すれば、実際に問題があるかどうかを確かめることができます。
■ メールの迷惑対策機能を活用しよう
現在、多くのメールサービスには迷惑メールを自動で振り分けるフィルター機能があります。
この設定を活用すれば、怪しいメールを事前にブロックし、受信トレイに届かないようにすることが可能です。
ドメインのブロック設定やフィルターの強化など、必要に応じてカスタマイズすることをおすすめします。
■ 判断に迷ったら、専門機関へ相談を
「これは本物かどうか分からない」「すでに情報を入力してしまったかもしれない」
そんなときは、以下のような公的機関に相談することが安心への第一歩です。
-
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口
-
消費者ホットライン(188)
-
フィッシング対策協議会(公式サイトあり)
一人で悩まず、専門の窓口に相談することで、被害の拡大を防ぎ、早期対応が可能になります。
安心してネットを使うために
インターネットは便利で生活を豊かにしてくれる反面、悪意を持った攻撃も存在します。
大切なのは、正しい知識と冷静な対応力です。
【緊急対策マニュアル】偽サイトに個人情報を入力してしまったときの対応方法

「入力してしまった…」と思ったら、すぐに行動を!
うっかり偽サイトにログイン情報やクレジットカード番号などを入力してしまった…。
そんな場面に直面したら、誰でも焦ってしまうものです。
しかし、慌てる必要はありません。被害を最小限に抑えるためには、できるだけ早く、正しい対処を取ることが何より大切です。
ここでは、今すぐ実行すべき対応を順を追ってご紹介します。
1. すぐにパスワードを変更する
まずは、偽サイトに入力してしまったIDやパスワードを使っているサービスにアクセスし、正規の公式サイトからパスワードを変更してください。
特に、ネットバンキングや通販サイトなど、金銭に関わるサービスを利用していた場合は、最優先で対応を行いましょう。
また、同じパスワードを他のサービスでも使っている場合は、すべてのサービスで異なるパスワードに変更することが大切です。
使い回しは被害の拡大を招く恐れがあります。
2. 金融機関・クレジットカード会社に連絡
もしカード情報や口座番号を入力してしまった場合は、すぐに利用している金融機関やカード会社に連絡を取りましょう。
事情を伝えたうえで、カードの一時停止や不正利用の監視など、必要な措置を講じてもらうことで、被害を防げる可能性があります。
その際には、情報を入力してしまった日時や、該当するサイト名をできるだけ詳しく伝えてください。
3. セキュリティソフトでウイルススキャンを実施
添付ファイルを開いたり、不審なリンクをクリックしてしまった場合は、ウイルス感染の恐れがあります。
すぐにパソコンやスマートフォンにインストールされているセキュリティソフトでウイルススキャンを行いましょう。
異常が検出された場合は、ソフトの指示に従って削除・駆除を行い、それでも不安が残るようであれば、専門のサポートや修理サービスに相談することをおすすめします。
4. 公的機関へ相談・報告する
情報漏えいや金銭的な被害が発生した、またはその可能性がある場合は、以下のような相談窓口に連絡することも重要です。
-
各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口
-
消費者ホットライン「188」
-
フィッシング対策協議会
-
国民生活センターまたは各地域の消費生活センター
ひとりで抱え込まず、専門機関の助けを借りて、早めに対応を進めましょう。
5. 覚えのない請求には応じない
「支払いが滞っています」「今すぐ料金を支払ってください」といった連絡が届いた場合は、本当に正当な請求かどうかを必ず確認してください。
正規の企業であれば、書面による通知や請求書が郵送されてくるのが一般的です。
突然の電話やメールでの請求には応じず、まずは落ち着いて、内容の真偽を見極めましょう。
少しでも不審に思ったら、支払う前に第三者へ相談することが重要です。
被害を防ぐために日頃の備えを
万が一のときでも、冷静に対処することで深刻な被害を避けることができます。
何よりも大切なのは、ふだんからセキュリティ意識を高く持つことです。
-
怪しいメールやSMSのリンクは開かない
-
個人情報の取り扱いには常に慎重に
-
パスワードは定期的に変更し、使い回しは避ける
こうした基本的な対策を心がけて、安心してインターネットを利用できる環境を整えていきましょう。
まとめ:不審なメールに惑わされないために——冷静な対応と正しい知識があなたを守る
迷惑メールの手口は日々巧妙になっており、誰もがその標的になる可能性があります。
完全に防ぐことは難しくても、正しい知識と落ち着いた判断があれば、被害を未然に防ぐことは十分に可能です。
今回ご紹介した対処法をあらかじめ知っておけば、万が一のときにも慌てず冷静に対応できるでしょう。
「何か変だな」「少しでも違和感がある」と感じたら、その直感を大切にして、安易にリンクを開いたり個人情報を入力したりしないように注意してください。
インターネットは私たちの生活を便利にしてくれる一方で、悪意を持って利用しようとする人が存在するのも事実です。
だからこそ、一人ひとりがセキュリティ意識を高め、情報リテラシーを身につけておくことが、被害を防ぐための何よりの備えになります。
この記事の内容が、少しでも皆さんの安心につながり、安全なインターネット利用の手助けとなれば幸いです。