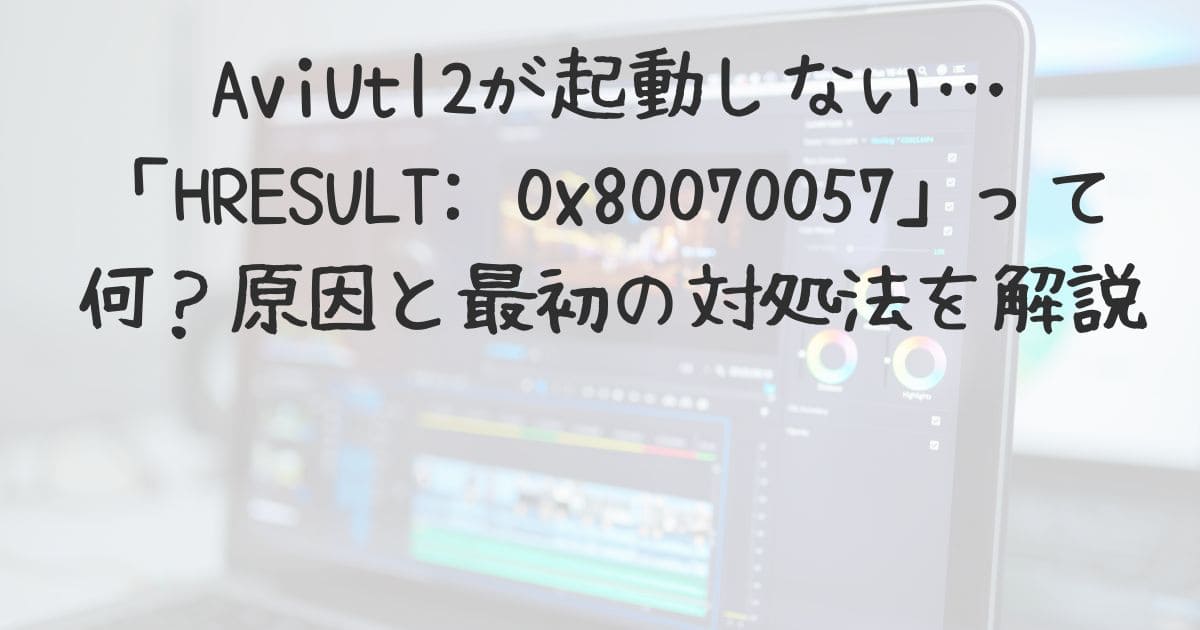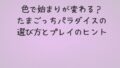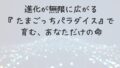最近、SNSなどで話題になっている「AviUtl ExEdit2 テスト版」。長年AviUtlを愛用してきた方にとっては、待望の新バージョンではないでしょうか。
しかし、せっかく導入してみたのに「うまく起動しない…?」と困っている方もいるかもしれません。
特に「HRESULT: 0x80070057」というエラーに直面すると、不安になる方も多いはずです。
このような英数字の羅列は一見難しそうに見えますが、実はWindowsの環境でよく報告されるエラーのひとつ。
今回はこのエラーの意味や起こる理由、最初に試してみたい基本的な対処法まで、やさしく解説していきます。
「HRESULT: 0x80070057」とはどういう意味?

このエラーコードは、簡単に言うと「渡されたパラメーター(情報)が正しくない」という内容を表しています。
つまり、パソコンが処理を進める際に受け取った情報に問題があると判断し、作業を中断してしまうのです。
このエラーはAviUtl2だけでなく、Windows全体のさまざまな場面で現れることがあります。たとえば:
-
Windowsアップデートの実行中
-
ハードディスクのフォーマット時
-
システムバックアップ作成中
-
アプリのインストール中
など、操作の種類に関係なく、広く起こり得るエラーです。
特に注意したいのは、このエラーを無視して作業を続けてしまうと、保存していたファイルが消えてしまったり、ドライブが初期化されてしまうリスクもあるということ。
だからこそ、表示されたときは早めの対応が肝心です。
エラーの原因は一つではない!よくある理由を確認

この「0x80070057」エラーが起こる背景には、いくつかの要因が考えられます。代表的な例を挙げてみましょう。
-
Windows Updateに不具合がある、あるいはアップデート途中で止まった
-
レジストリ(システムの設定データベース)に不正な値がある
-
古いデバイスドライバや、互換性のないドライバを使っている
-
システムファイルの一部が破損している
-
ハードディスクに物理的・論理的な障害が発生している
さらに見落としがちな原因として、「地域と言語の設定」で小数点記号が「,(カンマ)」に設定されていることが影響するケースもあります。
これは、数値の解釈に影響を与え、誤作動を招くことがあるのです。
まずはここから!基本のチェック&対処法

こうしたエラーが出たら、まず最初に試してみたいのが「再起動」です。
とても単純な方法ですが、一時的なエラーやメモリの問題であれば、再起動するだけで正常に戻るケースも意外と多くあります。
それでも改善しない場合は、Windowsに用意されている「トラブルシューティング」機能を活用してみましょう。
操作手順
-
「スタート」メニューから「設定」を開く
-
「更新とセキュリティ」を選択
-
左メニューから「トラブルシューティング」をクリック
-
「Windows Update」を選び、「トラブルシューティングツールの実行」をクリック
これにより、Windowsが自動でエラーの診断と一部修復を試みてくれます。
システムファイルの整備も有効な対策のひとつ

エラーが解消しない場合、Windows内部のシステムファイルが壊れている可能性もあります。
その際に使えるのが「SFC(システムファイルチェッカー)」と「DISM(展開イメージのサービスと管理)」というコマンドツールです。
これらを実行することで、破損したファイルを検出し、自動で修復を試みることができます。
コマンドの実行方法
-
「スタート」から「コマンドプロンプト(管理者)」を開く
-
以下のコマンドを1行ずつ入力してEnterキーを押す
→ システムファイルの整合性をチェックして修復します。
→ Windowsの更新コンポーネントや修復ファイルを補完します。
これらの手順を終えることで、ソフトウェア側の不調が回復し、AviUtl2の起動エラーが解消される可能性があります。
AviUtl2が起動しない本当の理由とは?レジストリ・ディスクエラー・グラボの相性を詳しく解説

「HRESULT: 0x80070057」というエラーコードの概要と、最初に試しておきたい基本的な対処法をご紹介しました。
その続きとして、より専門的な視点から原因を掘り下げていきます。
特に、レジストリ設定やハードディスクの状態、そしてGPUの対応状況といった“見落とされがちなポイント”に焦点を当てて解説していきます。
レジストリ編集は慎重に!正しく設定すれば解決に近づくことも
Windowsには「レジストリ」と呼ばれる仕組みがあり、システムやソフトの動作設定が細かく保存されています。
このレジストリの中には、AviUtl2の起動に影響する情報が含まれていることもあり、特定の設定を追加・変更することで改善される場合もあります。
たとえば、次のような手順が紹介されることがあります:
-
レジストリエディタを起動(検索窓に「regedit」と入力)
-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UXの場所まで進む -
「CopyFileBufferedSynchronousIo」というDWORD(32ビット)値を作成し、値を「1」に設定する
この設定変更が有効に働く場合もありますが、レジストリはWindowsの心臓部ともいえる重要な領域です。
操作を誤るとOSが正常に動作しなくなるリスクもあるため、必ずバックアップを取るか、知識のある人に相談した上で行うようにしましょう。
ハードディスクの異常も起動エラーの原因に?「エラーチェック」で状態確認を
AviUtl2が突然起動しなくなった場合、ハードディスクの不具合が関係している可能性もあります。
特に、ファイルの読み込みが途中で止まったり、編集作業に支障が出るようなトラブルが続いているなら、ディスク上のエラーを疑ってみましょう。
Windowsには簡単に実行できる「エラーチェック機能」が搭載されています。
チェック方法(GUI)
-
AviUtl2を保存しているドライブ(例:Dドライブ)を右クリック
-
「プロパティ」を選ぶ
-
「ツール」タブを開き、「エラーチェック」から「チェック」ボタンをクリック
これでシステムが自動的にドライブの状態を確認し、問題があれば修復を試みます。
より詳しく確認したい場合(コマンド)
-
「コマンドプロンプト(管理者)」を開く
-
以下のコマンドを入力してEnter
chkdsk D: /f
※「D:」はご自身の環境に合わせて変更してください。
※「/f」オプションはエラーがあった場合に自動修復を行う設定です。
AviUtl2に特有の「ROV非対応エラー」に要注意
AviUtl2で起動トラブルが発生する原因のひとつに、他のソフトにはない“特殊な要件”があります。
それが「ROV(Rasterizer Ordered Views)」という機能です。
ROVは、Direct3D 11.3以降で追加されたグラフィックス技術で、最新のAviUtl2ではこれに対応したGPU(グラフィックボード)が必須となっています。
もしお使いのPCのGPUがROVに対応していない場合、以下のようなメッセージが表示されることがあります:
-
「D3D ROVs not supported.」
-
「HRESULT: 0x80070057」
このような表示が出ると、残念ながらAviUtl2を起動することはできません。
解決するにはROV対応GPUへの切り替えが必須
現在のところ、ソフトウェア設定だけではROVに非対応なGPUの制限を回避するのは非常に困難です。
たとえば、AMDのRadeon HD 7700シリーズのような古いGPUはROVをサポートしておらず、AviUtl2の起動がそもそも不可能です。
一方、NVIDIAのGeForce RTXシリーズなど、比較的新しいGPUではROVにしっかり対応しているため、問題なく起動することが確認されています。
このように、AviUtl2を使うためには、ソフトだけでなくハードの対応状況も確認しておくことがとても大切です。
起動できない場合は、お使いのGPUがROV対応かどうかをまず調べてみましょう。
AviUtl2が起動しない理由はこれかも?プラグイン・設定・保存先・解凍ミスにご注意

これまでは、エラーコード「HRESULT: 0x80070057」の正体や、Windowsのシステム側での対処法、さらにGPUの対応状況について詳しく見てきました。
しかし、AviUtl2がうまく起動しない原因は、それだけにとどまりません。
ここからは、見落としやすい「プラグイン」「設定ファイル」「保存場所」「解凍方法」といった、細かなポイントに着目して解説していきます。
思い当たる点がある方は、ぜひチェックしてみてください。
プラグインの影響で起動しないことも!
AviUtl2は高機能な編集ソフトで、多くのユーザーが便利なプラグインを追加して使っています。
ですが、導入しているプラグインが原因でAviUtl2が立ち上がらなくなることも珍しくありません。
たとえば、次のような不具合が起こることがあります:
-
起動中にクラッシュする
-
画面が真っ黒のまま進まない
-
ウィンドウが表示されないまま終了する
こうした場合、まず疑うべきは「プラグインの不具合や競合」です。
問題が起きやすいプラグインの例
-
古いバージョンの
patch.aul -
「オブジェクトマネージャー」と「アルティメットプラグイン」の組み合わせ
-
拡張編集と互換性のないDLL形式のプラグイン
これらが原因である可能性があるため、一度すべてのプラグインをフォルダから退避(別の場所に移動)して、本体のみで起動できるかを確認することをおすすめします。
プラグインの見直しと更新で安定性アップ
原因となっているプラグインが特定できたら、以下のような対応をしてみましょう。
-
patch.aulは、必ず最新版を使用する -
「オブジェクトマネージャー」ではなく「オブジェクトエクスプローラ」を試す
このように、安定性や互換性を重視した構成にすることで、トラブルを未然に防げます。
設定ファイルが重すぎて起動を妨げることも
AviUtl2では、編集の自由度が高い分、設定値を高くしすぎると起動できなくなる場合があります。
とくに「最大画像サイズ」や「出力解像度」などを極端に大きく設定していると、読み込み時にフリーズしてしまうケースがあります。
対処法:設定ファイルのリセット
-
AviUtl2を保存しているフォルダを開く
-
中にある
aviutl.iniを見つける -
ファイルを削除する(※心配な方は事前にバックアップ)
-
AviUtl2を再起動して初期状態に戻す
これにより、過剰な設定値がリセットされ、スムーズに起動できる可能性があります。
保存場所の選び方にも注意が必要
AviUtl2をどこに保存しているかによっても、起動トラブルが発生することがあります。
特に、次のようなケースは注意が必要です。
-
フォルダ名やパスが非常に長い
-
フォルダ名に日本語(全角文字)を含んでいる
-
「デスクトップ」や「マイドキュメント」など、Windowsの保護領域に保存している
特に、Shift_JISの文字コード制限により、ファイルパスが259バイトを超えると正しく読み込めないことがあります。
おすすめの保存先
-
「C:\AviUtl」など、ルート直下に短いパスで保存する
-
英数字のみのフォルダ名にする(例:aviutl2)
これだけでも、環境依存のエラーを避けられることがあります。
ZIPファイルの解凍方法も見直してみよう
AviUtl2を公式サイトなどから入手した際、多くの方はZIP形式でダウンロードしているはずです。
このとき、どの解凍ツールを使ったかも重要なポイントです。
実は、Windows標準の「すべて展開」機能では、うまく展開できないケースが報告されています。
ファイルの属性やパーミッションが正しく反映されず、起動時に不具合を引き起こすことがあるのです。
安定した解凍ツールの例
-
7-Zip
-
WinRAR
-
Lhaplus(ラプラス)など
これらの専用ツールを使えば、より正確にファイルを展開でき、トラブル回避にもつながります。
AviUtl2をもっと安心・快適に使うために。再インストールやセキュリティ対策、新機能の魅力を解説

最後に「セキュリティ警告への対応方法」「再インストール時の注意点」、そして新しくなったAviUtl2の注目ポイントについて、わかりやすく解説していきます。
「WindowsによってPCが保護されました」と表示されたら?
AviUtl2を初めて起動した際、青い警告画面が出て驚いたという方もいるかもしれません。
「WindowsによってこのPCは保護されました」と表示されるこのメッセージは、Microsoftのセキュリティ機能「SmartScreen」によるものです。
この機能は、まだMicrosoftに登録されていない新しいアプリケーションを対象に、ウイルスなどのリスクを未然に防ぐために働く仕組みです。
AviUtl2は信頼性の高いフリーソフトですが、テスト版などは正式に認識されていないこともあり、この警告が表示されることがあります。
そんなときは、画面の中にある「詳細情報」をクリックし、「実行」ボタンを選択すれば問題なく起動できます。決してウイルスではないので、落ち着いて対応してくださいね。
どうしても起動しないときは再インストールも視野に
設定を見直しても、推奨スペックのPCを使っても、どうしても起動できない…。そんなときは、思い切ってAviUtl2を再インストールしてみましょう。以下の手順を踏めば、クリーンな状態で再セットアップできます。
AviUtl2を再インストールする手順
-
以前のAviUtl2フォルダを削除(必要に応じてバックアップを残しておく)
-
正規の配布元から最新のZIPファイルをダウンロード
-
7-Zipなどの専用ソフトで丁寧に解凍
-
Cドライブ直下(例:
C:\AviUtl2)のような、短くシンプルなフォルダに保存 -
初回起動時、「詳細情報」→「実行」を選んで起動
このように、手順をひとつずつ丁寧に確認して進めることで、余計なトラブルを避けることができます。
編集データが消えたときの最終手段は?
万が一、システムトラブルやディスクの異常によって、大切な編集データや素材ファイルが消えてしまった場合、自力での復旧はリスクが高いため注意が必要です。
誤った操作によって、取り戻せたはずのデータまで完全に消えてしまうことがあります。
もしものときは、データ復旧の専門サービスに相談するのが安心です。
たとえば「デジタルデータリカバリー」では、年中無休で無料診断を行っており、緊急時の相談先として頼れる存在です。
AviUtl2の新バージョンで何が変わったの?
今回リリースされた「AviUtl ExEdit2 テスト版」は、従来のAviUtlを土台から一新した大型アップデートとなっています。とくに注目すべきポイントは次の3つです。
1. 64bit対応でメモリ制限を突破
これまでのAviUtlは32bitアプリだったため、最大でも4GB程度までしかメモリを使用できませんでした。
今回の新バージョンでは、64bit対応によってより多くのメモリを活用でき、大容量の編集作業もスムーズに行えるようになりました。
2. インストーラーで導入が簡単に
これまではZIP解凍後にフォルダ構成を自分で調整する必要がありましたが、新バージョンはインストーラー形式になったことで、初心者でもボタンひとつで導入できるようになりました。
これにより、初めてAviUtlを使う方でもハードルがぐっと下がりました。
3. 対応環境に注意が必要
AviUtl2を快適に使うには、以下の環境が必要です:
-
OS:Windows 10(64bit)以降
-
グラフィックAPI:DirectX 11.3
-
CPU:AVX2に対応していること
-
GPU:ROV(Rasterizer Ordered Views)に対応していること
また、旧AviUtlで使っていたプラグインは、DLLを使っていないものであればある程度利用できますが、32bit DLL形式のプラグインには非対応となっているので注意が必要です。
まとめ:自分だけの編集環境を、安心して始めよう
AviUtl2は、慣れてくるほど自分の理想の編集スタイルに近づける、自由度の高いツールです。
最初の導入や設定でつまずくことがあっても、焦らずに一つひとつ確認していけば、必ず解決の糸口は見えてきます。
この記事が、あなたの動画編集環境づくりの参考になれば幸いです。これからAviUtl2と一緒に、楽しく快適な編集ライフを始めましょう!