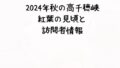2025年10月に実施された第28回ケアマネ試験(介護支援専門員実務研修受講試験)。
受験を終えた皆さんにとって気になるのは、「合格点は何点だったのか?」「難易度は去年より上がったのか?」という点ではないでしょうか。
この記事では、2025年度試験の最新データ・合格率・難易度の分析に加え、過去の傾向から導く合格基準点の予測を詳しく解説します。
また、次回受験に向けて今からできる勉強法やスケジュール戦略も紹介。
忙しい介護職の方でも無理なく合格を目指せるよう、実践的な学習法をわかりやすくまとめました。
「今年こそ合格したい」という方は、この記事で最新情報を押さえて一歩リードしましょう。
ケアマネ試験2025(第28回)— まず押さえておきたい基本情報

ここでは、2025年度(第28回)ケアマネ試験の基本情報を整理していきます。
試験日や出題形式を正確に把握しておくことで、効率的な学習計画が立てやすくなります。
試験日程・時間・出題方式
第28回ケアマネ試験は、2025年10月12日(日)に全国一斉で実施されました。
試験時間は120分で、全60問を解く構成です。
問題形式は「五肢複択式」で、5つの選択肢から2〜3つの正答を選ぶ方式です。
一部の選択肢を誤るとその問題全体が0点になるため、精度の高い知識が求められます。
| 試験項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施日 | 2025年10月12日(日) |
| 試験時間 | 120分 |
| 問題数 | 全60問 |
| 出題形式 | 五肢複択式(2〜3個選択) |
出題分野・問題構成と配点・形式(五肢複択式)
ケアマネ試験は、次の2つの大きな分野から構成されています。
それぞれの分野で基準点を満たす必要があり、どちらか一方でも不足すると不合格となります。
| 分野名 | 問題数 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 介護支援分野 | 25問 | 介護保険制度、ケアマネジメント、要介護認定など |
| 保健医療福祉サービス分野 | 35問 | 保健医療サービス(20問)、福祉サービス(15問) |
この試験では、単なる暗記ではなく、現場対応力や判断力も問われるため、事例問題や制度理解の深さが鍵になります。
時間配分と正確性のバランスを意識することが、合格への第一歩です。
最新データで見る合格率・受験者数(第27回を基準に)

続いて、2025年試験を分析する上で欠かせないのが、直近の第27回(2024年度)試験データです。
受験者数や合格率の推移を知ることで、試験全体の難易度や傾向を把握できます。
第27回(2024年度)の受験者数・合格者数・合格率(32.1%)
厚生労働省発表によると、第27回(2024年度)の受験者数は53,699人、合格者は17,228人でした。
合格率は32.1%で、過去20年で最も高い水準となりました。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 49,523人 | 10,742人 | 21.7% |
| 2023年度 | 51,086人 | 13,146人 | 25.7% |
| 2024年度 | 53,699人 | 17,228人 | 32.1% |
都道府県別・地域別の合格率データ(例:京都36.8%など)
地域ごとの合格率を見ても、全体的に高水準が続いています。
特に京都府では36.8%と全国平均を上回り、地方によって難易度の差が見られることも特徴です。
| 地域 | 合格率(2024年度) |
|---|---|
| 東京都 | 31.5% |
| 大阪府 | 33.4% |
| 京都府 | 36.8% |
| 福岡県 | 29.9% |
近年10年程度の推移と傾向(難易度変動の有無)
2015年以降の合格率推移を振り返ると、2018年度(第21回)に実務経験要件が厳格化された影響で、一時的に10.1%まで低下しました。
その後は緩やかに回復し、2024年度には過去最高水準を記録。
難易度は全体的に「やや易化傾向」にあるといえます。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2016 | 15.5% |
| 2018 | 10.1% |
| 2020 | 17.7% |
| 2022 | 21.7% |
| 2023 | 25.7% |
| 2024 | 32.1% |
この流れを見ると、受験者の実務経験や学習環境の整備が進み、合格しやすい時期に入っていると考えられます。
ただし、2025年度(第28回)は「介護支援分野」が難化傾向にあるとの声もあり、油断は禁物です。
合格基準点・合格点の仕組み【第27回データをもとに】

ここでは、ケアマネ試験の合格基準点と得点の仕組みについて整理します。
この試験では単に総合点だけでなく、各分野で一定の点数を取ることが重要になります。
基準点の考え方 ― 各分野で正答率70%基準、難易度補正あり
ケアマネ試験の合格基準は、原則として正答率70%が目安とされています。
ただし、問題の難易度が高い年度には補正(スライド)が行われ、基準点が引き下げられることがあります。
この「補正」は、受験者の得点分布を分析して決定され、試験の公平性を保つための重要な仕組みです。
| 分野 | 問題数 | 基準点の目安 | 過去の最低基準点 |
|---|---|---|---|
| 介護支援分野 | 25問 | 18点(約72%) | 13点(第21回・第23回) |
| 保健医療福祉サービス分野 | 35問 | 25点(約71%) | 21点(第22回) |
重要なのは、どちらか一方の分野でも基準点を下回ると不合格になる点です。
そのため、得意・不得意を作らず、両分野をバランスよく学ぶ必要があります。
第27回の実際の合格基準点:介護支援分野18点、保健医療福祉サービス分野25点
2024年度(第27回)の試験では、以下の基準点が発表されました。
| 年度 | 介護支援分野 | 保健医療福祉サービス分野 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 16点 | 23点 | 21.7% |
| 2023年度 | 17点 | 24点 | 25.7% |
| 2024年度 | 18点 | 25点 | 32.1% |
この結果から、第27回試験は全体的にやや易化傾向にあったと考えられます。
特に保健医療福祉サービス分野では、基本的な医療・福祉知識を問う問題が多く、得点しやすかったとの声が多く聞かれました。
過去の例での補正ケースと注意点
過去には、難易度が高かった年度で基準点が引き下げられたケースもあります。
たとえば2018年度(第21回)や2020年度(第23回)では、介護支援分野の基準点が13点まで下がりました。
| 年度 | 補正理由 | 補正後基準点 |
|---|---|---|
| 2018年度(第21回) | 実務経験要件改正による難易度上昇 | 13点 |
| 2020年度(第23回) | 制度改正・事例問題の複雑化 | 13点 |
つまり、難しい問題が出題された場合には、必ずしも70%を取れなくても合格の可能性があります。
合格点=相対評価で変動するという点を忘れないようにしましょう。
2025年(第28回)で予想されうる合格点ライン(推定)
2025年度試験では、2024年度と同様に保健医療福祉分野はやや易化、介護支援分野はやや難化傾向と見られています。
したがって、現時点での合格基準点の予想は以下の通りです。
| 分野 | 予想基準点 | 補足 |
|---|---|---|
| 介護支援分野 | 17〜18点 | 難化傾向を考慮 |
| 保健医療福祉サービス分野 | 24〜25点 | 例年並みまたはやや易化 |
この範囲で得点できれば、合格可能性は高いと考えられます。
最終的な正式発表は、厚生労働省および各都道府県発表(11月下旬予定)を確認しましょう。
2025年の難易度見通し — 難化?易化?その根拠と分析

第28回試験(2025年)の難易度については、受験生の声や予備校の分析から一定の傾向が見えてきています。
ここでは、現時点での評価とその背景を整理します。
受験生・口コミの予備的声(SNS・予備校見解など)
SNS上では、「介護支援分野が難しかった」という声が多数見られます。
一方で「保健医療サービス分野は基本問題が多く解きやすかった」との意見も多く、全体としては標準〜やや易しいという評価が目立ちます。
| 評価区分 | 割合(予備調査) | 主なコメント |
|---|---|---|
| 難しかった | 約30% | 介護支援分野で選択肢が紛らわしい |
| 標準 | 約45% | 例年と同程度、基礎知識重視 |
| 易しかった | 約25% | 保健医療分野が得点源になった |
制度改正・法改正・出題傾向変化がもたらす影響
2025年度試験では、2024年度に施行された介護保険制度の部分改正や「地域共生社会」関連の施策が出題される可能性があります。
また、2021年から進む重層的支援体制整備事業など、複数制度の横断的理解を問う問題も増加しています。
こうした背景から、「実務経験+制度理解」の両面を求める問題構成が続くと予測されます。
傾向から読み解く、2025年の「出題されやすいテーマ」予測
近年の出題傾向を踏まえると、以下のテーマが高確率で登場する可能性があります。
- 介護保険制度改正(第9期介護保険事業計画関連)
- 地域包括ケアシステム・地域共生社会
- 感染症対策・高齢者の栄養・口腔ケア
- 認知症施策推進大綱(2025改訂版)
- 多職種連携・インフォーマル支援の活用
これらは厚生労働省の施策方針にも直結する内容であり、特に制度理解と応用力を問う問題が増えると予想されます。
したがって、受験対策では単なる暗記にとどまらず、「なぜこの制度が必要なのか」を理解しておくことが重要です。
最新版対策 — 合格点を確実に超える学習戦略

ここからは、2025年版として最も効率的に合格点を超えるための勉強法を紹介します。
限られた時間の中で成果を最大化するには、計画・習慣・反復の3つが鍵となります。
推奨学習時間とスケジュール設定(2025版)
一般的にケアマネ試験の合格には、100〜200時間程度の学習が必要とされています。
仕事をしながら学ぶ人が多いため、1日あたり30〜60分でも良いので、継続が最も重要です。
| 学習期間 | 目安時間 | 主な取り組み内容 |
|---|---|---|
| 6〜4か月前 | 60時間 | 基礎知識の理解・テキストの精読 |
| 3〜2か月前 | 80時間 | 過去問演習・苦手分野の克服 |
| 1か月前〜直前 | 40時間 | 模擬試験・時間配分の練習 |
特に「試験直前の1か月」は、得点アップのラストスパート期間です。
模試や過去問で実戦感覚を磨き、時間配分を体に覚え込ませましょう。
過去問・模試の使い方(第27回以降の傾向反映版)
合格者の多くが共通して取り組んでいるのが、過去問の徹底演習です。
最低でも5年分は繰り返し解き、正答だけでなく「なぜ他の選択肢が誤りなのか」を説明できるレベルを目指しましょう。
| 演習回数 | 目標 |
|---|---|
| 1〜2回目 | 問題の構成を把握し、時間配分を確認 |
| 3〜5回目 | 解答理由を理解し、間違えた問題を再整理 |
| 6回目以降 | 全問正答を安定して出せる状態に仕上げる |
また、過去問だけではカバーしきれない新制度関連の問題は、各種予備校の「予想模試」を活用するのが有効です。
模試で得た結果を分析し、自分の弱点をリスト化しておくと効率的です。
弱点分析と補強の優先順位
限られた時間で成果を出すには、弱点を「見える化」することが重要です。
おすすめは、分野別にスプレッドシートを作り、得点率を色分けする方法です。
| 分野 | 得点率 | 優先度 |
|---|---|---|
| 介護支援分野 | 60% | 最優先 |
| 保健医療サービス | 75% | 中 |
| 福祉サービス | 80% | 低 |
苦手分野を放置すると、どんなに他が良くても合格できません。
逆に、苦手を克服すれば点数は一気に伸びるため、「弱点=伸びしろ」と捉えましょう。
法改正・最新ニュース・制度改変を抑える方法
ケアマネ試験では、毎年の制度改正が問題に反映されます。
2025年は特に、介護報酬改定・介護保険法改正・地域包括支援強化などが注目トピックです。
最新情報は厚生労働省の公式サイトや業界ニュースサイトを定期的に確認しましょう。
- 厚生労働省「介護保険最新情報」
- 中央法規・翔泳社などのケアマネ関連Webマガジン
- 都道府県福祉協議会・試験センターの公式リリース
また、ニュースを読む際は、「なぜこの改正が必要になったのか?」という背景まで理解することで、出題意図が見えてきます。
本番型トレーニング・時間配分戦略
本試験では、時間の使い方が合否を左右します。
ケアマネ試験は120分・60問ですから、1問あたり約2分が目安です。
過去問演習では、1問2分ルールを意識して練習しましょう。
| 時間配分目安 | 内容 |
|---|---|
| 0〜60分 | 保健医療福祉サービス分野(35問) |
| 60〜120分 | 介護支援分野(25問) |
解けない問題に時間をかけすぎず、まずは全問に目を通すことを意識しましょう。
見直し時間を10分程度確保できるように進めると安心です。
まとめ・今からできる最終準備
最後に、これまで紹介した内容を踏まえ、合格までの最終ステップを整理します。
焦らず、着実に「合格点を超える学習」を実行しましょう。
合格へのロードマップ(直近の行動プラン)
試験までの残り期間を有効に使うために、次のステップを意識してください。
| 期間 | 行動内容 |
|---|---|
| 〜試験2か月前 | 基礎固め+過去問3年分演習 |
| 〜試験1か月前 | 模擬試験で時間配分を確認 |
| 〜試験1週間前 | 弱点ノートの見直し・苦手分野集中 |
| 前日〜当日 | 早寝・体調管理・試験当日のシミュレーション |
大切なのは「完璧主義にならないこと」です。
9割覚えようとするよりも、7割を確実に得点できる状態を目指す方が合格に近づきます。
モチベーション維持のコツ・心構え
受験勉強は孤独になりがちですが、SNSやオンライン勉強会を活用することで、同じ目標を持つ仲間と励まし合えます。
また、模試や過去問の結果に一喜一憂せず、「昨日より1点でも伸びたらOK」という気持ちで継続することが大切です。
試験直前は不安が大きいですが、それは努力してきた証拠です。
最後まで学び続けたその姿勢こそが、介護支援専門員としての第一歩になります。
そして何より、この挑戦は必ずあなたのキャリアに価値をもたらします。
これまでの努力を信じて、本番では落ち着いて臨みましょう。
あなたの合格を心から応援しています。