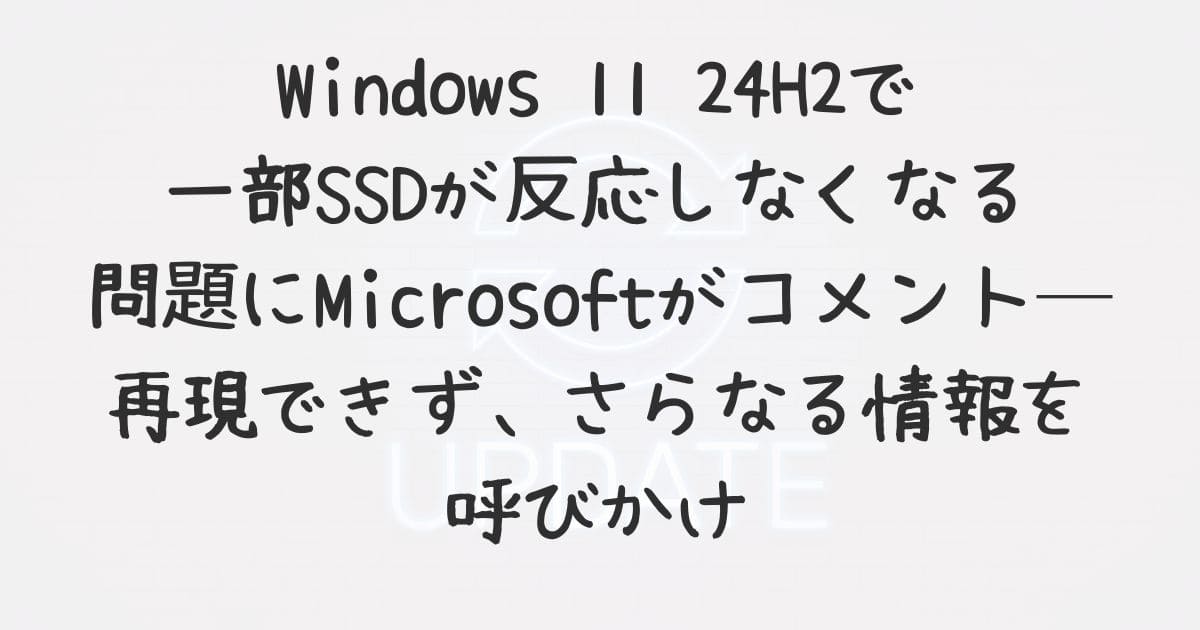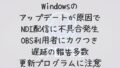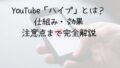Microsoftは現在、Windows 11の最新バージョン「24H2」において一部ユーザーから報告されている“SSDが突然認識されなくなる”という現象について調査を進めています。
ところが、同社が社内で行った複数の検証では、同様の不具合を再現することができなかったと明らかにしました。
どのような現象なのか?

ユーザーから寄せられた報告によると、特定の条件下でSSDが突然システム上から消えてしまうという不具合が発生しているようです。
具体的には、サイズの大きなファイル(例えば数十GB単位)を1つずつ保存したり、あるいは小さなファイルでも大量に書き込んで合計が数十GBを超えるような操作を行った際に、この問題が起きやすいとされています。
こうした状況下では、SSDが突然デバイスとして認識されなくなり、ファイルへのアクセスができなくなるケースが確認されています。
多くの場合はPCを再起動すれば正常に戻るようですが、中には再起動しても回復しない深刻な例も報告されており、原因の特定と対応が急がれています。
Microsoftによる調査の進捗と、ユーザーへの協力依頼

最近リリースされたセキュリティ更新プログラム(たとえばKB5063878など)を適用したWindows 11 バージョン24H2において、一部のユーザーから「ストレージデバイスが突然認識されなくなる」「ファイルが破損する」といった深刻な問題が報告されています。
これらの声を受け、Microsoftは社内での再現テストを実施しましたが、同様の症状を確認するには至らなかったとのことです。
現在は、ストレージ機器の製造パートナーと連携し、より実際の利用状況に近い環境で問題の再現性を追求している段階です。
また、Microsoftのカスタマーサポートには今のところ同様の不具合報告は寄せられていないと説明していますが、影響を受けた可能性があるユーザーには、「法人向けサポート窓口」や「フィードバック Hub」を通じて、できる限り詳細な情報の提供を求めています。
海外メディアの分析と追加報道
こうした状況について、海外テックメディア「TechRadar」は、SSDがPCから“完全に姿を消す”といったインパクトのある事例を紹介しながら、Microsoftがハードウェアベンダーと協力して調査にあたっていると報じています。
さらに「Windows Central」では、問題の原因が7月・8月に配信された更新プログラム(KB5063878など)にある可能性を指摘。
特に、「50GBを超える連続したデータ書き込み」や「ドライブの使用率が60%以上」といった条件が重なると、SSDやHDDがシステムから認識されなくなるリスクが高まるとの実験結果が紹介されています。
中でも、Phison製のコントローラを搭載したSSDに関連する報告が目立っており、影響が集中している可能性があるとしています。
ユーザーコミュニティや技術フォーラムでの反響
この不具合に関する議論は、Redditをはじめとする技術系フォーラムでも活発に行われています。
特に「r/hardware」では、多くのユーザーが自らの体験を共有しており、その中には次のような見解も見られました。
「Phison製のNANDコントローラを搭載し、なおかつDRAMを持たないSSDモデルでは、比較的少ない書き込みでも異常が起きやすい傾向があるようだ」
こうした指摘が増えており、実際にDRAMレスSSDに限定して問題が発生するという仮説も出始めています。
一方で、いくつかの専門メディア(たとえばPC GamerやIT Proなど)は、「これは単なる経年劣化による故障ではなく、OSアップデートが一部SSDのファームウェアや設計に想定外の影響を及ぼしている可能性がある」としており、ハードウェアとソフトウェアの相互作用を含めた丁寧な検証が必要だとの見解を示しています。
現在の状況と注目される分析ポイント

2025年8月12日に提供が始まったWindows 11(バージョン24H2)向けのセキュリティ更新プログラム「KB5063878」の導入後、一部のユーザーから「ストレージデバイスが急に認識されなくなる」「保存データが破損する」といったトラブルが報告されています。
とくに、SSDやHDDの空き容量が少なくなってきた状態(使用率60%以上)で、50GBを超えるような大容量ファイルを一度に書き込んだ場合に問題が生じやすい傾向があるようです。
また、ゲームの大規模なアップデート中にも同様のエラーが発生したケースがあり、調査の結果、Phison製のNANDコントローラを搭載しているSSDで症状が目立つとの報告も出ています。
ある技術系メディアによる独自テストでは、21種類のSSDを検証した結果、約半数にあたる12台でストレージが突然アクセス不能になる現象が発生。
中には再起動しても認識が回復しないモデルも含まれていました。対象となったSSDのブランドには、Western Digital、Corsair、ADATA、SK hynixなど、広く知られたメーカーが含まれており、特定の一社に限定された問題ではない可能性も示唆されています。
こうした状況にもかかわらず、Microsoftは現時点で不具合の公式認定は行っていないものの、報告の内容を把握しており、特にPhisonをはじめとするハードウェアメーカーと協力して、詳細な調査と原因究明を進めている段階です。
被害を防ぐためにユーザーができる対策

このような不具合が発生するリスクを少しでも抑えるため、エンジニアやセキュリティメディアでは以下のような予防策が推奨されています。
-
一度に大量のデータ(数十GB)をSSDに書き込まないこと
→ 書き込みはなるべく小分けにし、時間をおいて複数回に分けて行うのが望ましいとされています。 -
圧縮ファイルの展開も分割して実施すること
→ 例えば、数百個の大容量ファイルが含まれている圧縮フォルダを展開する場合、複数回に分けて処理することで負荷を分散できます。 -
該当する更新プログラム(KB5063878やKB5062660など)のアンインストールを検討
→ ただし、これらの更新にはセキュリティパッチも含まれているため、削除する際はリスクを十分に理解したうえで慎重に判断する必要があります。 -
データ保護の基本「3-2-1ルール」を実践すること
→ 重要なデータは「3つのコピーを」「2種類以上の媒体に保存し」「1つは外部(クラウドや外付けHDDなど)に保管する」ことで、万が一に備えましょう。
まとめ:いまは「原因調査中」──今後の情報にも注目を
今回のストレージ障害については、現段階ではまだ調査途中であり、Microsoftおよび関連ベンダーによる解析と対応策の検討が続いています。
修正パッチの配布時期、影響を受ける機種の詳細、または一時的な対処方法など、公式な案内が今後発表される可能性があります。
とくに最新のWindows環境においてSSDの不具合はシステム全体の安定性に直結するため、今後の動向に関心が高まっています。
日常的に大容量データを扱うユーザーや、Phison製SSDを使用している方は、引き続き最新情報に目を光らせておくことをおすすめします。