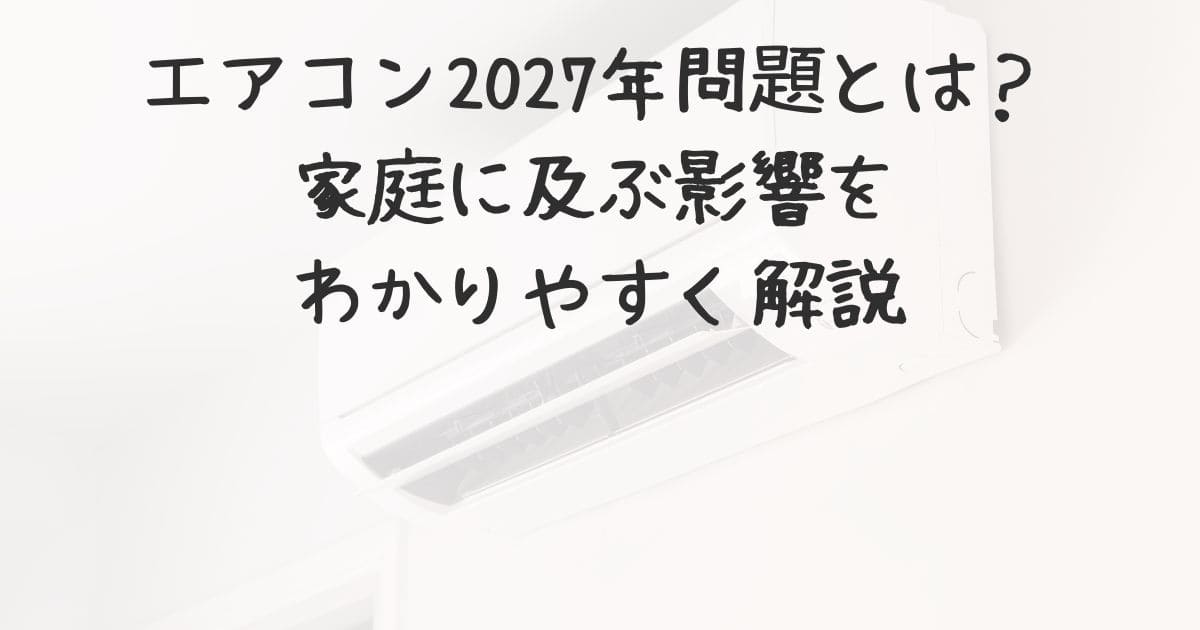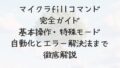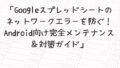こんにちは。
最近、「エアコン2027年問題」という言葉を耳にしたことはありませんか?
一見すると宣伝用の言い回しに感じるかもしれませんが、調べてみると私たちの生活に深く関わる重大な問題であることが見えてきます。
特に、年々厳しさを増す日本の夏を快適に乗り切るためには、エアコンの性能や選び方がこれまで以上に重要です。
ここでは、この問題の概要と注目される理由を整理してご紹介します。
■ エアコン2027年問題とは?

この問題の中心は、経済産業省が15年ぶりに家庭用エアコンの省エネ基準を大幅改定することにあります。
2027年度から新基準が適用され、基準を満たさない機種は製造・販売が禁止される予定です。
その結果、これまで一般的に購入できていたスタンダードモデルの多くが市場から姿を消す可能性があります。
■ 注目すべき指標「APF」とは?
新基準では特にAPF(通年エネルギー消費効率)が重要視されます。
APFは、1年間を通してエアコンがどれだけ効率的に冷暖房できるかを表す数値で、いわば“燃費”のような指標です。
この数値が高いほど省エネ性能に優れています。
具体的には、6畳用エアコンの現行基準APF5.8が、2027年度からはAPF6.6に引き上げられます。
これはおよそ13.8%の性能改善を意味します。
さらに、リビングで使われる4.0kWクラスでは、APF4.9→6.6へと約35%もの大幅な向上が必要となります。
この基準をクリアするため、メーカーには高い技術力とコスト負担が求められます。
■ なぜここまで厳しい基準が導入されるのか?
背景には、日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」という目標があります。
家庭で消費される電力の約25%をエアコンが占めているため、効率向上は環境対策に直結するのです。
加えて、冷媒ガスに関してもフロンガス削減の国際的な流れがあり、環境負荷の少ない新冷媒への移行が進められています。
こうした政策や世界的な動きが、新しい省エネ基準の導入を後押ししているのです。
2027年以降、エアコンは大幅値上げ?その理由をわかりやすく解説

「基準が厳しくなるのは理解したけど、実際の生活にどんな影響があるの?」
そんな疑問を持つ方も多いでしょう。
実は、2027年の省エネ基準改定によって、エアコンの価格が大幅に上昇する可能性が指摘されています。
■ 価格上昇の背景
現在販売されている家庭用エアコンのうち、約7割が新基準をクリアしていないといわれています。
つまり、これまで普及していた手頃な価格帯のモデルは、基準を満たさないため販売が続けられなくなる見込みです。
メーカーは新基準に対応するため、以下のような大幅な改良を行わなければなりません。
-
高性能コンプレッサーの採用
-
熱交換器の大型化や効率化
-
断熱材の高品質化
-
AI制御など高度なシステムの搭載
-
製造ラインや検査体制の強化
これらの技術向上には莫大なコストが発生し、最終的には製品価格の上昇につながります。
■ どれくらい値上がりするのか?
現在は安価なモデルが5万円前後から購入できますが、2027年以降は最低でも10万円前後になるとの予測もあります。
さらに、物価上昇の影響も加われば、1.5〜3万円、あるいはそれ以上の値上げも現実的です。
このように、エアコンが「気軽に買える家電」から高級家電に近い存在へと変わる時代が到来するかもしれません。
■ 値上げは避けられない?
性能が向上すること自体は喜ばしいことですが、その分のコスト増はどうしても避けられません。
「少し高くなる程度なら大丈夫」と考えていても、その“少し”が想像以上に大きな額になる可能性があります。
また、新モデルが登場することで旧型機種の値下がりも起こりにくくなり、早い段階での検討が重要です。
古いエアコンはそのまま使える?見過ごせないリスクをチェック

「2027年以降も、今のエアコンを使い続ければ問題ないのでは?」
そう考える方も多いでしょう。
確かに、新しい省エネ基準はこれから製造・販売される製品に対して適用されるため、現在使用中のエアコンがすぐに使えなくなるわけではありません。
しかし、安心して使い続けるにはいくつか注意点があります。
■ 使用はできるが、電気代が大きな負担に
古いエアコンは最新機種に比べると省エネ性能が低いため、同じ時間使用しても消費電力が多くなります。
例えば、20年前のモデルと最新の省エネタイプを比べると、年間で1万円以上電気代が高くなるケースもあります。
月単位では小さな差でも、数年単位で積み重なると家計への影響は無視できません。
■ 故障リスクと修理の難しさ
使い続ける場合、もう一つの問題は故障しやすくなること、そして修理が困難になることです。
-
エアコンの寿命はおよそ10〜15年。年数が経つとトラブルが増える
-
部品の製造終了により修理用パーツが手に入らない
-
古い冷媒ガスは価格高騰や供給停止で修理自体が不可能になる場合も
その結果、修理を依頼しても修理不可 → 買い替えという流れになるケースが増えています。
■ 賃貸住宅はさらに注意が必要
賃貸物件では、エアコン故障が長引くと入居者からクレームが入ったり、家賃減額の要求につながることもあります。
オーナーにとっては予期せぬコストとなり、早めの対応が重要です。
■ メンテナンスで延命可能だが限界も
定期的な業者によるメンテナンスや分解クリーニングは、効率を改善し消費電力を抑える効果があります。
しかし、製造から10年以上経ったモデルでは、クリーニング後に保証対象外となるケースもあるため注意が必要です。
古いエアコンを使い続ける場合は、こうしたリスクを理解しながら計画的に対応することが大切です。
エアコン買い替えのベストタイミングはいつ?賢く選ぶためのポイント

「結局、買い替えるならいつがいいの?」
多くの方が気になるこの疑問。結論から言えば、2025年から2026年末にかけてが最も賢い時期と考えられます。
■ 2026年以降は駆け込み需要で混乱必至
新しい省エネ基準が導入される2027年が近づくと、「値上がりする前に買っておこう」と考える人が急増します。
その結果、以下のような事態が想定されています。
-
人気モデルの在庫不足
-
本体価格・設置費用の大幅な上昇
-
工事業者の予約が取りにくい状況
特に最近の猛暑では、夏場の工事予約が1〜2か月待ちになることも珍しくありません。
在庫や価格がまだ落ち着いている今の時期に行動するのが、最も安心できる選択です。
■ 買い替え時に確認したいチェックポイント
エアコン選びでは、本体価格だけでなく長期的なコストも意識しましょう。
-
省エネマークの色を確認
-
緑色マーク:新基準達成(2027年以降も販売可能)
-
オレンジ色マーク:基準未達成(販売終了の可能性大)
-
-
APF(通年エネルギー消費効率)と年間消費電力量をチェック
-
本体価格が高めでも、省エネ性能の高いモデルなら電気代で差額を回収できる場合があります。
-
-
総コストで比較する
-
本体価格+設置費用+ランニングコスト(電気代)で判断
-
数年単位で考えると、省エネモデルの方がお得になるケースが多いです。
-
■ 2027年問題を逆手に取る賢い方法
-
今のうちに省エネ性能の高いモデルを購入
-
10年以上使っている機種、冷えが悪い・異音がする機種は早めに買い替え検討
-
クリーニングで寿命を延ばしつつ、交換時期を見極めるのも一つの手です。
■ まとめ
エアコンが10年以上経過していたり、最近調子が悪いと感じるなら、今こそ買い替えの好機です。
2027年問題を知って準備しておけば、無駄な出費を抑えつつ、快適で省エネな暮らしを手に入れられます。
「行動するなら今」――これが最も賢い選択といえるでしょう。