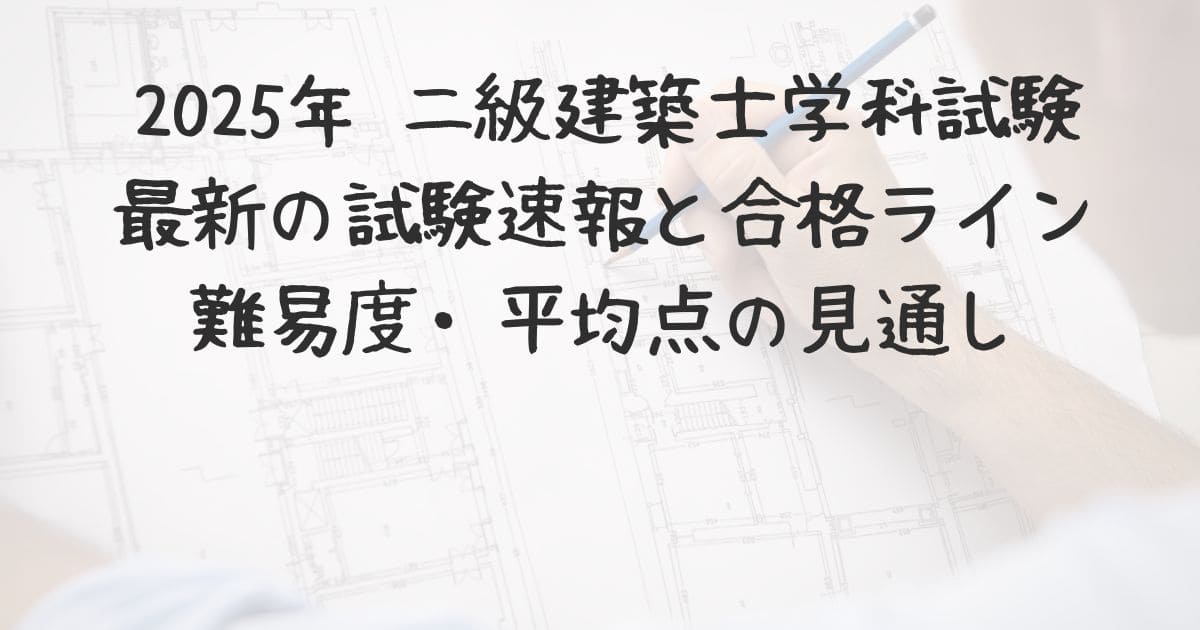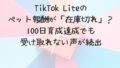2025年度の二級建築士学科試験を受験された皆さま、本当にお疲れさまでした。
この資格は、建築の専門分野で活躍するための重要な通過点であり、取得を目指して取り組む姿勢そのものが大変意義あるものです。
本記事では、今年実施された二級建築士(学科)試験について、最新の情報をもとに解説していきます。
合格基準の予想、難易度の傾向、平均点の見込みなど、気になる点をわかりやすくまとめました。
まずは、試験当日の概要からご紹介します。
■2025年 二級建築士・学科試験 実施概要
試験日:2025年7月6日(日)
二級建築士試験とは?学科と製図、それぞれの試験内容をわかりやすく解説

二級建築士の資格を取得するには、「学科試験」と「設計製図試験」という2つの試験を順番にクリアする必要があります。
どちらか一方ではなく、両方に合格してはじめて、正式に二級建築士としての道が開かれるのです。
■学科試験の概要|最初の関門を突破しよう
学科試験では、建築全般に関する知識が幅広く問われます。
出題は4つの科目からなり、それぞれ25問ずつ、合計100問が五肢択一形式で出題されます。
試験時間は合計6時間と長時間にわたるため、集中力と体力の両方が求められます。
●建築計画|多岐にわたる知識が求められる分野
この科目では、建築史や建築計画、環境工学、設備設計など、さまざまなトピックが扱われます。
建築史では、歴史的建築物の名称や特徴など、記憶力が問われる内容が中心です。
繰り返し出題される内容も多いため、過去問を活用した効率的な対策が有効です。
設備に関しては、空調、給排水、電気など、生活に密接に関わる仕組みの理解が重要になります。
複数の方式を比較しながら整理すると、より覚えやすくなるでしょう。
環境工学では計算問題が出題されることもあります。
過去の出題パターンに慣れておくことで、冷静に対応できるようになります。
●建築法規|暗記よりも「探す力」がカギ
建築基準法や建築士法、バリアフリー関連法規など、法律に関する知識を問うのがこの分野です。
「全部覚えないといけないのでは…」と不安になるかもしれませんが、試験では法令集の持ち込みが認められているため、必要なのは“暗記力”よりも“検索力”です。
日頃から法令集にマーカーを引いたり、インデックスを活用して使いやすくしておくことが、試験当日に大きな助けとなります。
この分野は得点源にもなりやすいため、効率よく対策しておきたいところです。
●建築構造|計算が苦手でもあきらめないで
構造分野は「一般構造」「構造力学」「材料」の3つに分かれており、特に構造力学では計算問題が中心となります。
数学に苦手意識がある人にはハードルが高く感じるかもしれませんが、必要な計算は基本的なものが多く、特別な数式を覚える必要はありません。
まずは解答の手順に慣れることから始めましょう。過去問を繰り返し解き、出題傾向をつかんでいくことで、徐々に自信がついてきます。
継続的に取り組むことで、安定して点が取れる分野に変えていくことが可能です。
●建築施工|現場の知識が強みになる分野
この科目では、施工計画や現場管理、鉄筋工事など、実際の建築現場に関わる内容が出題されます。
建築業界での実務経験がある方であれば、現場での体験がそのまま知識として役立つでしょう。
一方で経験がない場合でも、基本的な工程や用語を理解することから始めれば十分対応できます。
細かい部分にとらわれすぎず、まずは工事全体の流れや代表的な作業内容を把握することを意識しましょう。
■設計製図試験の実態とは?|実技試験で問われる力

学科試験を突破すると、次は設計製図試験に進みます。
この試験は、事前に発表された課題に基づいて図面を作成する“実技形式”の試験です。
試験時間は5時間(休憩なし)と長丁場ですが、限られた時間内に正確かつ完成度の高い図面を仕上げるスキルが求められます。
ここ数年では、「保育所を備えた集合住宅」や「カフェ付き二世帯住宅」など、より実際の生活に即したテーマが多く出題されています。
図面の見栄えだけでなく、設計条件の読み取り、暮らしやすさに配慮した間取り、そして社会的背景に対する理解まで、幅広い視点での対応力が問われます。
初めて製図試験に取り組む人にとっては難しく感じられるかもしれませんが、反復練習を重ねることで確実に力がついていきます。
作図とプランニングを繰り返すことが、合格への一番の近道です。
二級建築士試験は、単なる暗記だけではなく、実務に即した知識と応用力が求められる試験です。
着実な準備を重ねて、自信を持って本番に挑みましょう。
二級建築士試験に合格するための条件とは?|学科・製図それぞれの評価基準を解説

二級建築士の資格を取得するためには、「学科試験」と「設計製図試験」の両方に合格する必要があります。
それぞれに明確な合格基準が設けられており、どちらも高いレベルの知識とスキルが求められます。事前に評価のルールをしっかり理解しておくことが、合格への第一歩です。
■ 学科試験の合格基準
学科試験は4つの科目で構成されており、それぞれに最低ラインが設けられています。
おおよその目安として、各科目で13点以上を取ることが求められます(※年度によって若干の変動あり)。
加えて、全体の合計点が60点以上であることも必須条件です。
つまり、もし一科目で基準点に届かない場合は、他の科目で高得点を取っていたとしても不合格になってしまいます。
このため、得意分野に偏った学習では不十分です。
すべての科目をバランスよく対策して、全体的な底上げを図ることが非常に重要になります。
■ 設計製図試験の評価方法
設計製図試験は、筆記式の学科試験とは異なり、点数による評価ではなく「ランク制」によって合否が決まります。
評価はランクⅠ〜Ⅳの4段階で行われ、合格となるのは最も高い「ランクⅠ」のみです。
それ以下のランク(Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ)に分類された場合は、残念ながら不合格となります。
図面が一見丁寧に仕上がっていても、細かな条件の見落としや記載ミスがあると評価が下がることもあります。
たとえば設計条件の読み違いや、寸法・納まりのミスといった小さなミスでも、積み重なることで大きな減点につながるのです。
そのため、製図試験では「正確さ」と「注意深さ」が大きな鍵になります。
図面を完成させる作図技術に加えて、細部への意識を忘れない集中力も合否を分ける重要な要素です。
二級建築士試験は、学科と製図の両方を確実にクリアする必要があります。
それぞれの評価基準を理解し、自分の弱点を見極めながらバランスのとれた学習を心がけましょう。
必要であれば、「勉強の進め方」や「過去の合格ライン傾向」などの追加情報もご提供可能です。
二級建築士試験の合格率と難易度は?その背景と受験の壁を詳しく解説

二級建築士試験は、合格率が約22〜25%前後とされる難関資格です。
これはつまり、4人に1人が合格するかどうかという狭き門であり、毎年多くの受験者が真剣に挑む試験であることを物語っています。
■ 難しいとされるのはなぜ?二級建築士試験が高難度な理由
試験の合格率が低い背景には、いくつかの要因が存在します。
単に出題範囲が広いだけでなく、制度そのものが高いハードルを設けている点に注目すべきです。
●受験するためにも条件がある
まず、二級建築士試験は誰でも受けられるわけではありません。
受験には、建築系の学歴や特定の資格、あるいは実務経験といった条件が必要とされます。
たとえば、指定の大学や専門学校で建築関連の課程を修了していること、建築設備士の資格を取得していること、または7年以上の建築実務経験があること、などが該当します。
現在は制度の見直しにより、実務経験がなくても試験自体は受けられるようになっていますが、免許登録にはやはり実務経験が求められるため、実質的なハードルは依然として高いままです。
●学科と製図、2段階で求められる力が異なる
試験が「学科」と「設計製図」に分かれている点も難易度を押し上げています。
学科では知識の広さと正確さが問われ、一方の製図試験では実務に近い作図スキルや空間構成力が求められます。全く異なる能力をバランスよく養わなければならないのです。
また、製図試験の課題テーマは学科試験の直前に発表されるため、準備期間が限られていることも受験者にとっては大きな負担となります。
●厳しい評価基準が合格を阻む
学科試験には、各科目に最低点が設定されており、合計点が合格基準を満たしていても、1科目でも基準点を下回れば不合格となる厳しいルールが存在します。
さらに製図試験は「ランクⅠ〜Ⅳ」の4段階で評価され、合格できるのは最上位のランクⅠのみ。
図面全体の完成度が高く見えても、設計条件の読み違いや細かな記載ミスがあると評価が下がり、結果的に不合格となることもあります。
●長期間にわたる学習とメンタルの維持が必要
もうひとつの大きな課題は、長期戦となる受験勉強を継続する精神力です。
試験は年に1度しか実施されないため、計画的に学習を進めながらモチベーションを維持することが欠かせません。
私自身の経験でも、学習の手が止まりそうになるときには「この資格を取って、どんな建築物を手がけたいのか」を具体的に想像し、気持ちを奮い立たせることが支えになりました。
夢や目標を明確に持ち続けることは、長い学習期間を乗り越える大きな力になります。
二級建築士試験は決して簡単な試験ではありませんが、合格すれば確かな専門性と信頼を得られる資格です。
その価値に見合う努力を惜しまず、前向きにチャレンジしてみてください。
二級建築士に合格するための勉強法|効率よく力を伸ばすポイントとは?

二級建築士の資格取得を目指す中で、「どんな勉強法が効果的なのか」と悩む方も多いことでしょう。
ここでは、合格を目指すうえで知っておきたい学習の進め方や勉強のコツを、実体験や受験ノウハウを交えながらわかりやすくご紹介します。
■ 学科試験の対策|計画性と過去問活用がカギ
まずは、学習計画を立てることから始めましょう。
二級建築士の学科試験に必要とされる学習時間は、一般的に500〜700時間ほどと言われています。
この時間を試験日から逆算してスケジューリングすることで、焦りを感じにくくなり、学習のリズムも整いやすくなります。
目標が明確になると、モチベーションの維持にもつながります。
次に重視すべきは「過去問の繰り返し演習」です。
実際の試験では、過去に出題された内容と類似する問題が多く出る傾向にあります。
何度も問題を解くことで出題パターンに慣れ、解答スピードや正確性も自然と身についていきます。
間違えた問題は、なぜ誤ったのかを丁寧に振り返りましょう。
解説を読んで理解を深めることで、知識がしっかりと定着します。
また、特定の科目に苦手意識がある場合も、避けずに基礎から丁寧に取り組むことが重要です。
学科試験ではすべての科目で基準点を超える必要があるため、得意・不得意を分けずにバランスよく学ぶことが合格への近道です。
■ 設計製図試験の対策|完成させる練習と設計意図の理解がポイント
学科試験を突破すると、次に待っているのが設計製図試験です。
この試験では、限られた時間内で図面を正確に、かつ美しく仕上げる技術が求められます。
作図スピードはもちろん、建物の使いやすさや機能性を考慮した設計力も問われます。
木造建築がテーマの場合は「矩計図」や「部分詳細図」など、細かな納まりまで表現する力が必要です。
また、鉄筋コンクリート造が出題されることもあるため、構造の種類に応じた知識も求められます。
とくに意識したいのは、「制限時間内に図面を完成させる」こと。
未完成のまま提出すると評価の対象外になってしまうため、まずは図面を最後まで描ききる練習から始めるのが効果的です。
さらに大切なのが、課題の背景にある「設計意図」を読み取り、それを図面に落とし込む力です。
たとえば、世代間の同居を意識した住宅や、地域交流をテーマとした施設など、単なる間取りの作成ではなく、社会的なニーズに応える設計提案が求められます。
「計画の要点」と呼ばれる記述式の課題では、図面に込めた考えを文章でわかりやすく伝える必要があります。論理的かつ簡潔な表現を心がけ、日頃から文章練習も行っておくと安心です。
■ 独学が不安な場合は講座や添削指導も活用しよう
とくに製図対策では、独学だと不安を感じる方も少なくありません。
実際に手ごたえを感じられるようになるには時間がかかるため、専門講師による添削指導や、通信講座、専門学校などを利用するのも有効です。
プロの視点からアドバイスを受けることで、自分では気づけないミスやクセに早めに対処でき、効率的に実力を伸ばすことができます。
勉強法に「正解」はありませんが、共通して大切なのは「コツコツ継続すること」です。
焦らず、あきらめず、少しずつ前進していく姿勢が合格への一番の力になります。
一級建築士と二級建築士の違いとは?―資格ごとの特徴と将来設計への影響を解説

建築士には「一級建築士」と「二級建築士」という2種類の国家資格があり、それぞれに特徴や役割、そして将来的なキャリアへの影響が異なります。
単なる等級の違いではなく、扱える建物の規模や仕事内容、進めるキャリアの方向性にも大きな差があります。
■ 一級建築士|幅広い建築物に対応できるハイレベル資格
一級建築士は、国土交通大臣によって認定される国家資格です。
この資格があれば、建物の大きさや構造形式、用途にかかわらず、あらゆる種類の建築物の設計や工事監理を行うことができます。
住宅のような小規模なものから、超高層ビル、大型商業施設、スポーツスタジアム、さらには都市計画に関連するプロジェクトまで、非常に幅広い分野で活躍することが可能です。
まさに「建築の専門家」としての実力を証明する資格と言えるでしょう。
■ 二級建築士|住宅や中規模建築を担う地域密着型のプロ
一方、二級建築士は都道府県知事の認可を受ける国家資格で、主に戸建住宅や小規模〜中規模の建物を対象としています。
構造や用途に応じて扱える建物に一定の制限がありますが、その分、一般の住宅や地域の施設など、私たちの暮らしに直結する建物の設計に携わることができます。
実生活に身近な建物を手がけられるという意味で、非常に実用的かつ社会貢献度の高い資格です。
■ 難易度の違い|合格率にもはっきりとした差が
一級建築士と二級建築士では、試験の難しさにも明確な違いがあります。
【一級建築士】
-
学科試験の合格率:15〜20%前後
-
製図試験の合格率:約30%
-
総合合格率:約10%程度
【二級建築士】
-
学科試験の合格率:35〜40%
-
製図試験の合格率:約50%
-
総合合格率:約22〜25%
一級建築士は、何年もかけて合格を目指す方も多く、非常に難関な資格として知られています。
対して、二級建築士は初めて国家資格に挑戦する方にも取り組みやすく、実務経験とあわせてスキルを高めやすい点が魅力です。
■ 年収と就職先の違い
収入面や就職先についても、資格によってある程度の違いがあります。
一級建築士は平均で700万〜800万円ほどの年収とされており、ゼネコンや大手設計事務所、官公庁など大規模な建築物を扱う環境で活躍することが多くなります。
責任が重い分、待遇にも反映されやすいのが特徴です。
一方、二級建築士の平均年収はおよそ350万〜500万円程度とされ、住宅メーカーや地域密着の工務店などで働くケースが中心です。
より地域に根ざした建築活動を行いたい方には、二級建築士の働き方が合っているかもしれません。
■ 二級から一級へ――段階的なキャリアアップも可能
まず二級建築士を取得し、実務経験を積んだのちに一級建築士を目指すというルートも、多くの受験者が選んでいます。
段階的にスキルアップしていくことで、仕事の幅も広がり、より大きなプロジェクトに携われるようになります。
「最初は二級でしっかり経験を積み、将来的に一級へ」という流れは、実務に即した現実的なキャリアパスとしておすすめです。
建築士の資格は、どちらも社会的に高い信頼と専門性を備えたものです。
どの資格を目指すかは、将来どんな建物を設計したいのか、どのような働き方を望むのかによって選択するのが理想です。
自身の目標やライフプランに合った資格を選び、理想のキャリアを築いていきましょう。
二級建築士とは?―住まいを支える建築の専門資格

二級建築士は、建築に関する専門的な知識と技術を持ち、各都道府県知事から免許を受けて活動する国家資格者です。
主に一般住宅など、私たちの生活に身近な建物の設計や工事監理を行うことができ、「暮らしをカタチにするプロフェッショナル」として、地域社会に深く関わっています。
■ 設計できる建物の範囲とは?
二級建築士が手がけられる建物には、構造や規模に応じて明確な制限があります。
【木造建築の場合】
-
階数:3階建てまで
-
高さ:13メートル以下
-
軒高:9メートル以下
-
延べ面積:1,000平方メートル未満
【鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨造(S造)の場合】
-
高さ:13メートル以下
-
軒高:9メートル以下
-
延べ面積:100平方メートル以下
このように、高層ビルや大規模な施設には対応できないものの、一般的な住宅や店舗、地域の中小規模の建築には十分対応可能な資格です。
■ 人の暮らしに寄り添う設計の魅力
「大きな建物は担当できないから、活躍の場が狭いのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし実際には、二級建築士が設計する住宅こそ、住む人の価値観やライフスタイルに合わせた、きめ細やかな配慮が求められる分野です。
家族構成の変化や将来の暮らしを見据えた設計、安全性や快適性を備えた空間づくりなど、施主の思いをくみ取る力と、それを形にする設計力が不可欠です。
人と暮らしに寄り添う建築こそ、二級建築士が最も力を発揮できるフィールドだと言えるでしょう。
■ 資格がもたらす信頼とキャリアの広がり
二級建築士の資格は、建築業界での就職やキャリアアップにおいて大きな強みとなります。
設計事務所やハウスメーカー、地域密着型の工務店など、さまざまな職場で即戦力としての評価を受けやすくなります。
また、独立して設計事務所を開業する際にも、資格があることで顧客からの信頼を得やすくなり、仕事の幅も大きく広がります。
自分の設計力や責任感を示す“確かな証”として、社会的な信用にもつながる重要な資格です。
「人の暮らしを支える建築に関わりたい」「地域に根ざした設計を手がけたい」――
そんな思いを抱く方にとって、二級建築士は理想に近づくための大きな一歩になるはずです。
資格取得に向けて、今できる準備から始めてみませんか?未来の選択肢が、きっと広がっていくはずです。
まとめ|二級建築士を目指すすべての方へ
二級建築士の資格を取得することは、簡単なことではありません。
学科と製図という異なる分野の試験を突破するには、長期的な学習と、あきらめない強い気持ちが必要です。
それでも、この挑戦には十分な価値があります。
合格することで、建築の専門家としての信用を得られるだけでなく、あなたのキャリアの可能性も大きく広がります。
「どんな建物をつくりたいか」「誰のために設計したいか」――
その想いを忘れずに、一歩ずつ着実に前に進んでください。
積み重ねた努力は、いつか必ずあなたの力になります。
あなたが描く理想の未来が実現することを、心から応援しています。