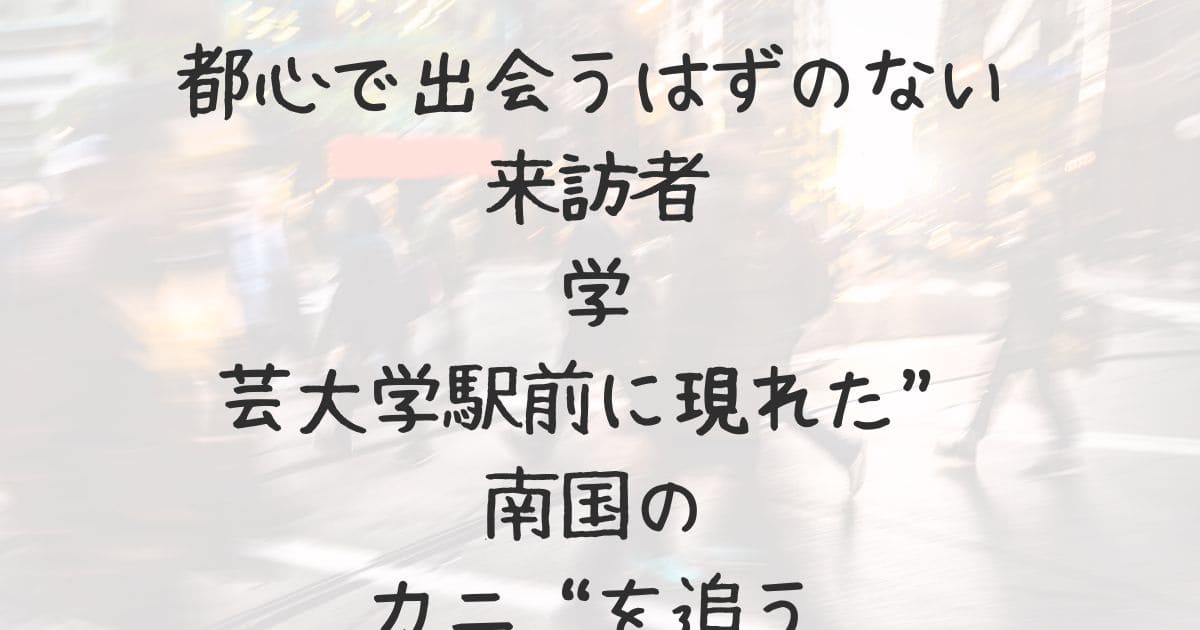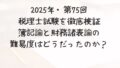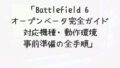■ 路上を歩くカニの姿がSNSで話題に
2025年8月初旬、SNS上で注目を集めたのは、東京・目黒区の学芸大学駅周辺で撮影された一本の動画でした。
その映像には、ビルや住宅が立ち並ぶ都会の歩道を、一匹のカニがゆっくりと横歩きしている様子が収められていました。
通勤・通学の人々が日常的に行き交う場所で起きたこの“非日常的”な出来事に、ネットユーザーたちは一斉に反応。
「サンマで有名な目黒に、今度はカニまで?」というようなユーモアを交えたコメントが相次ぎ、投稿は一気に広まりました。
■ 都会の舗道を行く正体不明のカニ

カニが初めて目撃されたのは、6月28日深夜のこと。
駅から数十メートル離れた車道沿いを歩く姿を通行人が偶然見つけ、その様子をスマートフォンで記録しました。その後、SNSで映像が拡散されたことにより、専門家が検証に乗り出します。
甲羅の形状や脚の比率などから、目撃されたカニは「ミナミオカガニ」である可能性が高いとされています。
このカニは日本国内では沖縄や先島諸島といった温暖な南西諸島地域の沿岸部に生息しており、都心で見かけるような種類ではないことが判明しました。
■ ミナミオカガニとはどんな生き物?

この“ミナミオカガニ”は、以下のような特徴を持つとされています:
-
生息地:主に琉球列島(沖縄や宮古島など)の砂浜や海岸近く
-
生活環境:水辺から陸地に移動して生活する「陸生」のカニで、海に戻るのは卵が孵化して幼生期を過ごすときだけ
-
行動特性:夜行性が強く、日中に人の目に触れることは滅多にない
つまり、今回目撃された個体が東京、それも住宅街の駅前に出現したというのは、極めて異例であると言えるのです。
■ 一度きりではなかった!? 再び現れたカニ

さらに驚くべきことに、カニは一度だけ目撃されたわけではありません。
初回から約1か月後の7月26日夜、今度は学芸大学駅から少し離れたコンビニ前でも、またしてもカニが歩いている様子が確認されました。
6月に発見された個体はすでに保護され、ペットショップを通じて新しい飼い主のもとへ引き取られていたため、今回の出現は「別の個体ではないか?」という推測が浮上します。
つまり、この周辺でカニが複数存在している可能性があるということになります。
■ なぜ“南方のカニ”が東京に?

このような生態を持つミナミオカガニが、なぜ東京都心の住宅街に姿を現したのか。
その理由については、複数の仮説が挙げられています。なかでも有力とされているのは以下の2つです。
① ペットとして飼われていた個体が逃げた、または捨てられた
現在では、都内にも熱帯性の魚類や爬虫類、甲殻類などを専門に扱うペットショップが数多く存在しています。
こうした店舗では、観賞用として希少な種類のカニが販売されることも珍しくありません。
飼育中のケージや水槽が破損したり、何らかの理由で飼い主が放棄した場合には、飼育下の個体が屋外に出てしまう可能性があります。
特に今回のように、発見されたカニが人に慣れている様子を見せたことからも、飼育されていた痕跡がうかがえるという指摘があります。
② 南方から運ばれた貨物や園芸品に混入していた
もう一つの可能性として挙げられているのが、南西諸島から本州へ輸送された園芸用の石材や観葉植物などに幼体が紛れ込み、そのまま物流経路を通って東京に運ばれたという説です。
実際、観葉植物の土や鉢に小さな虫や両生類が潜んでいるケースは珍しくなく、カニのような生き物が混入してしまう可能性も否定できません。
ただし今回のカニはある程度の大きさに成長していたため、「物流ルートで都内まで運ばれたにしては、やや不自然では?」という専門家の意見もあります。
飲食店から逃げた可能性は否定
一部では「飲食店で使われていたカニが逃げ出したのでは」といった憶測も出ましたが、これは当該エリアの飲食店関係者により完全に否定されています。
もんじゃ焼き店の店主は取材に対し、「うちで使っているのはズワイガニのむき身で、生きたカニを仕入れて調理することはしていない」と説明しており、店舗からの“脱走”の可能性は極めて低いとみられています。
■ ミナミオカガニの“味”に迫る――本当に食べられるのか?

● 茹でたときの香りは食欲をそそるが…
沖縄在住のフィールドライターが自身のブログで紹介していた体験記によると、ミナミオカガニを採取してすぐに塩ゆでにした際、立ち上る湯気にはガザミやモクズガニを思わせる香ばしさが感じられたそうです。
しかしそのゆで汁を口にしてみると、期待していた風味とはかけ離れていたといいます。
口の中に広がったのは、土をそのまま煮込んだような独特の“泥の香り”。
味に深みがなく、全体的にうま味の要素が極めて薄いという印象だったと記されていました。
● 可食部はごく一部、殻の硬さにも難あり
このカニの食べられる部位についても、同レポートでは厳しい評価が並んでいます。
特に評価されたのは両側のハサミ部分で、そこに詰まった白身は「確かにカニらしい味わいがあった」と報告されていました。
しかし、脚は非常に細く、身はほとんど取れず、胴体部分にいたっては筋肉量も少ないため、食用としての価値は限定的といえます。
また、問題なのはその“殻の硬さ”。非常に厚くて頑丈であり、ハサミで割るだけでも大きな労力が必要だったとのこと。
食べる以前の問題として、調理の手間が非常にかかる点が難点とされています。
● ミソの風味は“泥そのもの”――泥抜きしても変わらず
さらに致命的だったのが、カニミソの風味です。
茹でる前の段階で泥抜きを試みたものの、完全に臭みを取り除くことはできず、加熱後も“泥のえぐみ”が舌に残るという結果に。
食材としてのポテンシャルは非常に低いというのが実食者の総評でした。
なお、沖縄ではヤシガニのような大型の陸生甲殻類が郷土料理として根付いている例がありますが、ミナミオカガニについてはそのような文化がほとんど存在しておらず、食用として扱われていない理由も「風味の問題にあるのでは」とされています。
● 総合評価:都会で見かけても“味わう”より“観察”を
このようなレポートを総合すると、ミナミオカガニは――
-
調理中の香りは良いが、味そのものは非常に淡泊
-
食べられる部分が少なく、労力と得られる量が釣り合わない
-
ミソは泥臭く、泥抜きしても風味が改善されにくい
……といった特徴から、「観賞対象としては面白いが、食材としては適さない」という結論に至っています。
都心で出会ったとしても、無理に食用にしようとは考えず、そっと見守るのが最善と言えるでしょう。
■ 意外と多い!? 都市部での“野生生物との遭遇体験”

今回のカニ騒動を受けて、SNSや地域メディアでは「自分も変わった生き物を見たことがある」という体験談が続々と寄せられました。
以下では、都内を中心とした“街中での生き物目撃例”をいくつかご紹介します。
● 荒川の土手に群れるカニの大行進
東京都北区から足立区にかけて広がる荒川の河川敷では、日没後になるとクロベンケイガニの群れが歩道を横断する様子が確認されています。
図書館の地域資料にも記録が残っており、ランニング中の人がうっかり踏んでしまいそうになることもあるほどの出現率だそうです。
● 都心の湧水に定着するサワガニ
文京区の斜面沿いに点在する湧水ポイントでは、年間を通して水温が安定していることから、日本在来種であるサワガニが繁殖・定着しています。
区が公開している生物多様性レポートにも記載されており、都市の中にひっそりと生きる在来種の姿に驚く人も多いようです。
● 江戸川・浦安エリアでもカニの姿が
東京湾の内湾部にあたる江戸川区や浦安市の沿岸部では、ベンケイガニやクロベンケイガニが干潟や草地に生息しており、近年では内陸の河川でもその姿が確認されることがあります。
特に水辺の環境が整っている場所では、こうしたカニが活動する様子を観察できる機会が増えているようです。
● 熱帯魚やサンゴまで──変わる東京湾の生態
ここ数年の海水温の上昇によって、東京湾奥ではチョウチョウウオなどの熱帯魚やサンゴの自生が報告されています。
もはや“亜熱帯化”といっても過言ではない変化が進んでおり、研究者の間でも注視されている現象です。
● インコが桜を落とす!? 外来鳥の影響も
都内の公園などでは、逃げ出した外来種「ワカケホンセイインコ」の群れが定着しており、桜の開花シーズンになると、花柄を食いちぎって次々と花を落としていく姿が観察されています。
小金井市や鳥類保護団体もその被害を報告しており、生態系や景観への影響が懸念されています。
● ヤドカリやサワガニも“身近な隣人”に
SNSや個人ブログの投稿によると、「雨が降った翌朝に自宅の車庫でサワガニを見つけた」「大阪のオフィス街で深夜にヤドカリと遭遇した」といった事例も複数寄せられています。
かつては珍しいとされていた生き物との“偶然の出会い”が、今や都市生活の中にも潜んでいることが見て取れます。
都心に暮らしていても、ふとした瞬間に自然と接点を持つ場面は確実に増えてきています。
カニに限らず、思いもよらない生き物との遭遇を楽しむ心のゆとりを持ちつつ、その存在が示す“環境の変化”にもぜひ目を向けていきたいものです。
■ SNSがざわついたカニ騒動──笑いと心配が交錯したネットの反応

● ネット上ではユーモアと驚きが大爆発
学芸大学駅前でカニが出没したという話題が広まると、SNS「X(旧Twitter)」ではユニークなコメントが続々と投稿されました。
「目黒といえばサンマ、今度はカニ!?」「令和の学大は甲殻類まで通勤してくるのか」といった軽妙なツッコミが相次ぎ、ネット上では一大ムーブメントに。
YouTubeでもこの珍事件を紹介する速報動画が投稿され、コメント欄には「まさか都内の通勤路でカニと遭遇するとは」と驚きの声が殺到。再生回数は数十万を超え、大きな注目を集めました。
● 珍客を心配する声も拡大
目撃時の様子を伝えるニュースによれば、駅前にいた人々はその場で「このカニどうすれば?」「どこに通報すればいいの?」と騒然となり、小さなカニのまわりに人だかりができたといいます。
SNSでも「このまま冬を迎えたら死んでしまうのでは」「早く安全な場所に保護されてほしい」といった心配の声が多く見られました。
6月に発見された個体は、都内の爬虫類・エキゾチックアニマル専門店「PROP」に持ち込まれ、その後、店頭に掲示された貼り紙を通じて新たな飼い主が見つかりました。
無事に引き取られたという報告には、「まるで保護猫や保護犬のようだ」と称賛する声も寄せられています。
● 憶測が飛び交い、陰謀論も登場!?
当初は「どこかの飲食店から逃げたのでは?」という憶測も流れましたが、現地のもんじゃ焼き店の店主が「当店では生きたカニは使用しておらず、調理用のむき身だけ」と明言したことで、“店からの脱走説”は早々に否定されました。
その後は、「個人が飼っていたものを逃がしたのでは?」「物流に紛れてやってきた?」「あるいは鳥にくわえられて空から落ちた?」など、真偽不明な説が次々と登場。
都市で起きた意外な出来事は、瞬く間にさまざまな想像をかき立てたのです。
■ 専門家が挙げた3つの“上陸ルート”とは?

| 仮説 | 考えられる理由 | 主な情報源 |
|---|---|---|
| ① ペットとして飼育されていた個体が逃げ出した説 | 都内にはオカガニ類を扱う専門ショップがあり、6月に保護された個体も“人慣れしていた”様子があった | FNN、khb東日本放送 |
| ② 園芸品や貨物に紛れて都心まで来た説 | 南西諸島から運ばれた観葉植物や石材に幼体が混ざる可能性があるが、今回の個体は成長しすぎていて不自然との指摘も | 国立科学博物館 小松浩典氏 |
| ③ 気候変動により東京でも生息可能になった説 | 東京湾でサンゴや熱帯魚が定着しているなど、都市の“亜熱帯化”が進んでいる証拠がある | 葛西臨海水族園プロジェクト、各種テレビ報道 |
現在のところ、もっとも有力とされるのは①の「ペット逃走説」ですが、②や③が重なっている可能性も完全には否定できません。
特に、環境変化と人間の行動が複雑に絡み合う現代では、単一の原因に絞るのは難しいようです。
■ 「都会=自然がない」はもう昔?野生が戻りつつある都市の風景

最近では、都市に生き物が戻りつつある現象が各地で観察されています。例えば――
-
東京湾の湾奥部では、色とりどりのサンゴが繁殖し、チョウチョウウオなどの熱帯魚が泳ぐ姿が目撃されるようになりました。
-
都内の公園や緑地では、外来種であるワカケホンセイインコの群れが定着し、春には桜の花を食い荒らす被害も発生しています。
-
荒川沿いでは夜になるとベンケイガニが道を横断する“カニロード”が出現するなど、都市部における生態系の多様化が静かに進んでいます。
今回のカニの出現も、そうした「都市における自然の復権」を可視化する象徴的な出来事として、専門家の間でも注目されています。
■ 路上で野生動物に遭遇したときの正しい対応

都市部でも思いがけず野生生物と出会うことが増えつつあります。そうしたとき、どのように対応すればよいのでしょうか?
専門家や動物保護団体は以下のような行動を推奨しています。
-
直接触れず、一定の距離を保つこと
陸生カニなどは防御反応としてハサミを振り上げることもあり、思わぬケガの原因になります。 -
スマートフォンなどで写真・動画を記録する
撮影時には位置情報も含めておくと、後に種類の特定や報告の際に役立ちます。 -
地元の自治体や動物愛護センターに連絡する
東京都には「外来動物通報フォーム」も整備されています。 -
段ボールなどで囲い、一時的に保護する場合は直射日光を避けること
ただし水を無暗にかけたり、触れたりするのは避けてください。 -
自分で飼育しないこと
無許可での飼育は法律に抵触する場合があるため、安易に持ち帰らないよう注意が必要です。
■ まとめ──“カニ騒動”が浮き彫りにした現代社会の課題
学芸大学駅前に突如現れたカニのニュースは、単なる珍事件にとどまりませんでした。
この出来事は次のような複数の重要な問いを私たちに投げかけています。
-
都市インフラと自然が交錯する場所に、私たちはどう対応すべきか
-
ペットの遺棄や物流管理の在り方に、見直しの余地はないのか
-
温暖化によって変わりゆく都市の生態系をどう受け止めるべきか
偶然の出会いが、ひとつの気づきにつながることもあります。
「見つけたら保護すべきか、見守るべきか?」──その判断を迫られる場面で、私たちがいかに冷静に、そして環境と共生する意識を持てるかが、これからの都市生活においてますます問われていくのではないでしょうか。
カニ一匹の出現が、人と自然との新しい関係を考える“きっかけ”になったことは間違いありません。