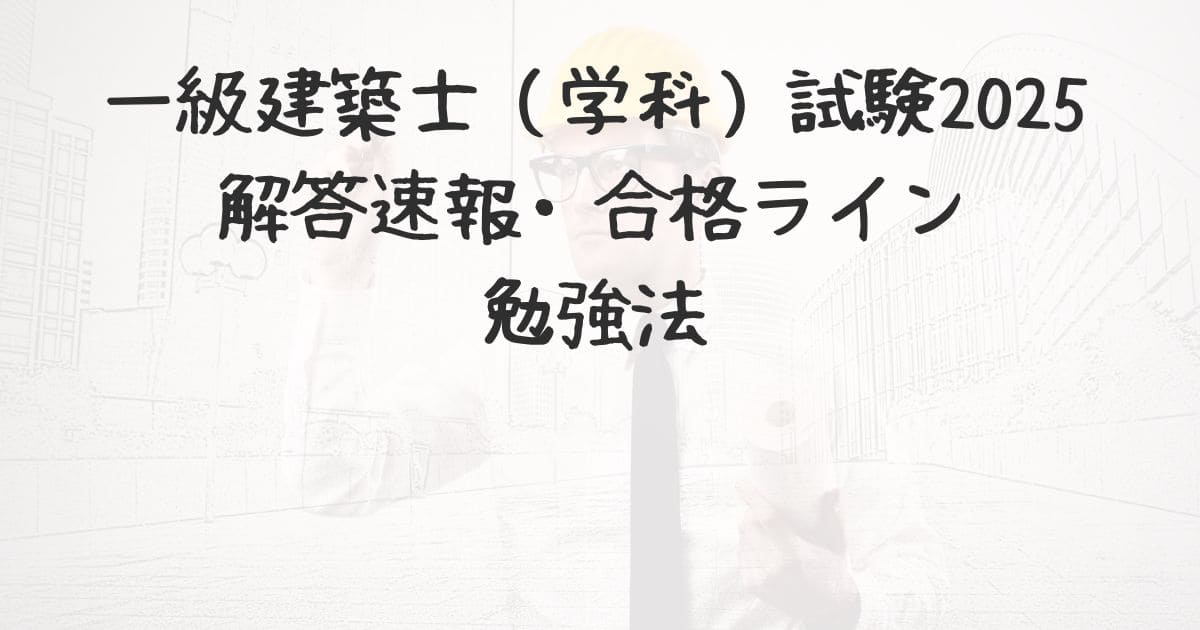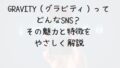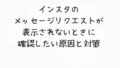一級建築士という大きな目標に向かって学科試験に挑戦された皆さま、本当にお疲れさまでした。
その一歩を踏み出されたことだけでも、十分に価値のある素晴らしい行動だと思います。
この記事では、2025年の一級建築士(学科)試験について、試験当日の解答速報の見方や合格ラインの予測、難易度の振り返り、さらに次に備えるための勉強方法などを、できるだけやさしく、分かりやすい表現でまとめてみました。
初めての受験で不安だった方、再チャレンジで緊張された方、それぞれにいろいろな思いがあったことと思います。
そんな皆さんが、少しでも安心できるような情報をお届けしたくて、この記事を丁寧に書いています。
最後まで読んでいただけたら嬉しいです。
そして、皆さんがこれから一歩ずつ前に進むためのヒントになりますように。
試験当日の速報情報

一級建築士の解答速報は、試験終了後すぐに確認したいという方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、速報がチェックできるおすすめの方法をご紹介します。
- TAC公式サイト:例年通り、当日の夕方ごろに正答番号がPDFで公開される予定です。試験後の落ち着いたタイミングで確認できます。
- 日建学院サイト:夜の20時30分からライブ形式の解説配信があります。どの問題が難しかったか、どこに注意すべきだったかが分かりやすく説明されるので、理解を深めるのにぴったりです。
- 総合資格学院サイト:19時ごろから利用できる「即日採点サービス」が人気。自己採点がしやすく、合否の目安を早く知りたい方には特におすすめです。
さらに、SNSでもリアルタイムの情報収集が可能です。
X(旧Twitter)で「#一級建築士 解答速報」や「#学科試験」などのハッシュタグを検索すると、受験された方々の感想や速報リンクが次々と投稿されていて、タイムリーな情報を手に入れることができますよ。
試験が終わった直後は、ほっと一息つきながら速報を確認することで、これまでの努力を振り返る時間にもなります。焦らず、ゆっくりチェックしてみてくださいね。
試験当日に必要な持ち物・服装チェックリスト

受験日は緊張でバタバタしがちなので、事前の準備が安心につながります。
- 受験票・身分証明書
- 会場への入室時に必ず必要です。前日のうちにカバンへ入れておくのがおすすめ。
- 法令集(付せんの位置も確認)
- 使用可能な法令集かどうか、付せんやインデックスの数・種類にもルールがあります。事前に確認を。
- 腕時計(試験会場に時計がない場合があります)
- デジタル・アラーム付きはNGな場合も。アナログのシンプルなものが安心です。
- 鉛筆・消しゴム・マークシート用のペン
- シャープペンよりもHB鉛筆が推奨されることが多く、芯が折れないよう複数本持って行きましょう。
- 羽織ものやストール(冷房対策)
- 冷房が効きすぎて寒く感じる会場もあるため、体温調整できる服装が大切です。ひざ掛けがあるとさらに安心。
- おにぎり・チョコなどの軽食(午後の集中力維持に)
- 昼食後の眠気や空腹を防ぐために、手軽に食べられてエネルギー補給ができるおやつを用意しておくとよいでしょう。
合格ラインと平均点の速報まとめ
2025年のボーダー予想については、TACや総合資格学院、日建学院などの大手資格スクール各社から、例年通り速報値が発表されています。
今年も受験者の皆さんにとって気になるポイントのひとつですよね。
- 合格基準は、5科目の総得点が92点以上であることに加えて、各科目ごとに設けられた足切り点(最低基準点)をすべてクリアする必要があります。つまり、全体で点数を取れていても、1科目でも基準点を下回ると不合格になってしまう仕組みです。
- 各科目の基準点は年度によって若干の変動がありますが、目安としてはそれぞれ10〜15点前後とされています。とくに「構造」や「法規」は難易度が高く、基準点を下回りやすい傾向にあるので注意が必要です。
- また、過去3年間の全国平均の合格率を振り返ると、2022年が21.0%、2023年は16.2%、2024年が23.3%と推移しており、年度ごとの難易度や出題傾向によって合格率が大きく変動しているのが分かります。
このように、合格ラインは固定ではなく、その年の問題の難易度や平均点に応じて変動するため、まずは速報で自己採点をして、自分の現状を客観的に把握することが大切です。
2025年の出題傾向と難易度

今年は、「環境・設備」や「脱炭素」などの持続可能性に関する出題が特に目立ち、時代の流れを反映した内容になっていた印象です。
省エネ法や新しい建築物省エネ基準の内容を問う問題もあり、普段から法改正やトレンドにアンテナを張っていた方にとっては手応えがあったかもしれません。
特に法規の分野では、複雑な条文の読み取りや適用判断を求める問題が出され、試験全体の中でも「難しい」と感じた方が多かったようです。
SNS上でも「今年の法規はひときわ難しかった」「環境分野の出題が想定以上だった」といった声が多く見られ、昨年と比較して全体的に難易度が上がったという感想が目立ちました。
ただ、その分だけ皆さんが積み重ねてきた努力も、きっと高く評価されるはずです。
難しいと感じた問題が多かったとしても、周りの受験生も同じ条件で受けていることを忘れずに。
あきらめず、冷静に自己採点や振り返りを進めていきましょうね。
合格後の手続きとこれからの道のり

学科に合格すると次に待っているのは、いよいよ「設計製図試験」です。
これは一級建築士試験のもう一つの大きな山場であり、実務力と論理的思考を問われる重要なステップとなります。
製図試験は、知識だけではなく「スピード」と「精度」が問われるため、準備には想像以上に時間と体力が必要になります。
課題の理解から作図練習、時間配分の習得まで、段階的な学習が求められるため、できるだけ早い段階から製図の練習を始めることが合格の近道です。
予備校や通信講座の模擬課題を活用しながら、1日1枚でも手を動かす習慣をつけると、実力が着実についてきますよ。
また、製図試験の準備と並行して行うべきなのが、「免許登録」の手続きです。
晴れて学科と製図の両方に合格した後、正式に一級建築士として登録するためには、一定の事務的手続きを済ませる必要があります。
- 登録申請には「実務経験を証明する書類」や「住民票」「写真」など、いくつかの書類の提出が求められます。書類の不備があると受付が遅れる場合もありますので、早めの準備を心がけてください。
- また、登録には手数料(登録免許税や登録料)がかかります。2025年現在で約6万円程度の費用がかかるため、事前に用意しておくと安心です。
- 書類を提出してから登録証の交付までは、平均して2〜3か月ほどかかります。登録時期に合わせて就職活動や転職を検討している方は、余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
製図の勉強と事務手続きを同時進行するのは少し大変に感じるかもしれませんが、どちらも大切な一歩です。無理のない範囲で計画的に取り組んでいきましょう。
勉強法・教材おすすめガイド

来年以降に向けて再チャレンジを考えている方も、これから受験を目指そうとしている方も、今のうちから勉強法を見直すことが、合格への近道になります。
勉強の方法や使う教材、学習スケジュールなどを少し工夫するだけで、効率がぐんとアップします。
- スタディングや日建学院などの通信講座は、スキマ時間を上手に活用したい方にぴったりです。通勤時間やちょっとした空き時間にスマホで動画講義を見られるので、忙しい社会人や主婦の方でも取り組みやすいのが魅力です。音声講義を聞きながら家事をする「ながら勉強」もおすすめですよ。
- 『分野別過去問題集500+125問』のようなテキストは、重要ポイントを分野ごとに整理してくれていて、効率よく復習するのにとても役立ちます。過去問演習を通じて「出題傾向」や「よく狙われる箇所」に自然と気づけるようになり、理解が深まっていくのを実感できます。
- また、書き込み式のノートや、一問一答形式のアプリを取り入れると、繰り返し確認する習慣がつきやすくなります。視覚的にまとめることで、記憶にも残りやすくなります。
大切なのは、無理をしないことです。短期集中ではなく、日々少しずつでも継続して学ぶことが、最終的には大きな自信になります。
気持ちにゆとりを持って、今の自分に合った学び方を見つけていきましょうね。
まとめ|一歩ずつ確実に進んでいこう
一級建築士の試験は決して簡単な道のりではありませんが、それだけに合格したときの喜びや、努力を重ねてきた自分自身への誇りは、本当に大きなものです。
長い時間をかけて積み上げてきた知識や経験が形になる瞬間は、何ものにも代えがたい達成感に包まれるはずです。
今年、この挑戦に真剣に取り組まれた皆さんに、心からの拍手とエールをお送りしたいと思います。
途中でくじけそうになったり、不安でいっぱいになったこともきっとあったかもしれません。でも、そんな中で最後まで走り抜けたこと、それ自体が素晴らしいことです。
この記事が、試験後の振り返りや今後の行動のヒントとして、少しでも皆さんのお役に立てれば何よりです。
これから製図試験に進まれる方も、また来年に向けて準備を始める方も、自分らしいペースで歩んでいってくださいね。
いつでも、そっと背中を押してくれるような存在でありたいと思っています。
これからも、あなたの歩みを心から応援しています。