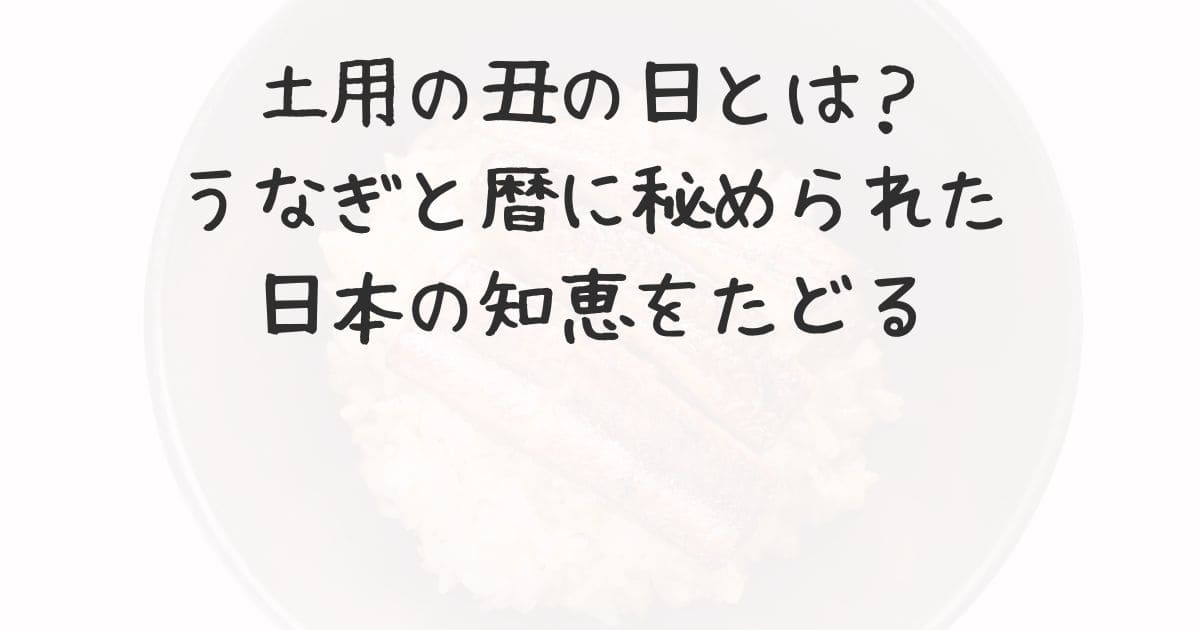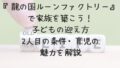「土用の丑の日」ってどういう日?本当の意味を知っていますか?
夏になると、街のスーパーや飲食店で「うなぎ」の特設コーナーが目に留まり、食欲をそそる香ばしい匂いに心が惹かれることがありますよね。
そのタイミングでよく話題にのぼるのが「土用の丑の日」です。
この日といえば「うなぎを食べる日」として広く知られていますが、なぜこの日が特別なのか、そもそも「丑の日」とは何なのか――その意味や背景まで理解している人は少ないかもしれません。
実はこの行事、単なる年中行事ではなく、古代中国から伝わった思想や、日本の気候風土と深く関わって生まれた文化的な背景を持っています。
今回は、そんな「土用の丑の日」の由来や成り立ちを、丁寧にひもといてみましょう。
「土用」も「丑の日」も、古代の暦と思想から生まれた言葉

「土用(どよう)」という言葉を耳にしたことはあるけれど、正確な意味までは分からないという方も多いのではないでしょうか。
「土用」とは、季節の変わり目を表す約18日間の期間のことです。
実は土用は夏だけでなく、春・夏・秋・冬のすべてに存在しており、1年のうちに4回巡ってきます。
これは、古代中国の「陰陽五行説」に基づいた考え方で、「木・火・金・水」の四元素に季節をあてはめ、それらを入れ替える“隙間”を「土」として補うという思想に由来しています。
一方、「丑の日」とは、干支(えと)の十二支の中で「丑(うし)」にあたる日のことです。
干支は年だけでなく日にちにも使われており、12日ごとに「丑の日」が訪れます。
この2つを組み合わせたのが「土用の丑の日」。
つまり、「四季の切り替え時期(土用)」にあたる期間中に、十二支の「丑」が巡ってくる日こそが「土用の丑の日」というわけです。
その中でも、特に注目されているのが「夏の土用の丑の日」。
理由はとてもシンプルで、夏は気温が高く体力を消耗しやすいため、栄養価の高い食べ物をとって元気をつけようという生活の知恵がそこに込められているのです。
うなぎが主役になった理由とは? 平賀源内がきっかけの説が有力

「土用の丑の日にうなぎを食べる」という習慣が始まったきっかけとして、最も有名な説があります。
それは、江戸時代の博学者・平賀源内にまつわるエピソードです。
ある夏の日、うなぎの売れ行きが悪くて困っていたうなぎ屋が、源内に相談を持ちかけたといいます。
そこで彼は、「『土用の丑の日にうなぎを』と看板を出してみてはどうか」と助言しました。
店はその言葉通りに貼り紙を掲げたところ、なんと大勢の客が集まり、大繁盛したのだとか。
この出来事が人々の印象に残り、「丑の日にうなぎを食べると良い」というイメージが広まったとされています。
これが現在の風習のはじまりとなったという説です。
また、当時の人々の間では「丑の日には“う”のつく食べ物を食べると夏負けしない」といった言い伝えもありました。
うなぎだけでなく、うどん、梅干し、瓜(うり)なども、体に良いとされる食材として注目されていたのです。
このように、民間信仰に根ざした風習と、商業的な工夫が結びついたことで、「土用の丑の日=うなぎを食べる日」という文化が日本中に定着していったのです。
土用の丑の日は1回とは限らない?実は2回ある年もあるんです

「土用の丑の日」と聞くと、「年に一度の夏の行事」と思い込んでいる方も多いかもしれません。
ですが、実はその年の暦のめぐり方によっては、丑の日が2回あることもあるのです。
この理由は、「干支」が12日ごとに一巡する仕組みにあります。
土用の期間はおよそ18日間とされているため、そのあいだに2度「丑の日」が訪れる年があるのです。
そうした年には、最初に巡ってくる日を「一の丑(いちのうし)」、次の丑の日を「二の丑(にのうし)」と呼び、それぞれ縁起の良い日として扱われています。
2025年の夏は“2回”の丑の日が登場
では、2025年はどうなのでしょうか?
この年は、夏の土用の期間中に丑の日が2回ある年にあたります。
- 一の丑:2025年7月19日(土)
- 二の丑:2025年7月31日(木)
このように、同じ夏の土用に2度丑の日があることはそれほど珍しいことではなく、実際に飲食業界では「一の丑」と「二の丑」の両方で“うなぎフェア”を展開するお店も少なくありません。
どちらの日にうなぎを食べてもまったく問題ありませんが、世間的には「一の丑」の方が先にやってくるぶん、注目度が高く、メディアや販促でも大きく取り上げられる傾向にあります。
食べ方の工夫で体への負担も軽減できる

ただし、うなぎは脂が多く、消化に時間がかかるという側面もあります。
そのため、胃腸が弱っている方や年配の方は、食べる量や調理方法に少し気を配ることも大切です。
例えば、蒲焼きのようにタレをたっぷり使うよりも、白焼きにしてあっさり仕上げたり、大根おろしやわさびなどの薬味を添えることで、より消化しやすく、風味も引き立てることができます。
「たくさん食べれば良い」ではなく、自分の体調に合わせて、必要な栄養を無理なく取り入れるのが理想的な“夏のうなぎの楽しみ方”なのかもしれません。
うなぎが苦手でも大丈夫。“う”のつく食べ物で夏を元気に過ごそう

栄養価が高く夏バテ予防に効果的なうなぎですが、「ちょっと苦手」「高くて手が出せない」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときは、昔から伝わる知恵――「丑の日には“う”のつく食べ物を食べると元気になれる」という考え方に目を向けてみてはいかがでしょうか。
実際、身近な食材の中にも、“う”のつくものはたくさんあり、それぞれが夏の体調管理に役立ってくれる優れた食材です。
以下にいくつかご紹介します。
● うどん
暑さで食欲が落ちがちな夏でも、のど越しの良いうどんならスルリと食べられるという方も多いはず。
冷たくしても温かくしても美味しく、胃腸への負担も少ないため、体力が落ちているときにもぴったりの一品です。
● 梅干し
梅干しに含まれるクエン酸には、疲労物質の分解やエネルギー代謝を助ける働きがあります。
さっぱりとした酸味が食欲を刺激してくれるだけでなく、塩分補給にもなるので、夏場には特に重宝される食材です。
● 瓜類(きゅうり・スイカ・冬瓜など)
瓜系の野菜や果物は水分をたっぷり含んでおり、体の熱を内側から冷ましてくれる作用があります。
とくにスイカやきゅうりは、食べやすさと涼感の両方を兼ね備えた夏の救世主。夏バテ防止や熱中症対策にもおすすめです。
こうした「う」のつく食材を日々の食事にうまく取り入れれば、うなぎを食べなくても、丑の日の知恵を活かして健康に夏を乗り切ることができるでしょう。
【補足】子どもにもおすすめ!“う”のつく食材で楽しく補給

うなぎは子どもにとっては少しクセが強く、苦手に感じることもありますよね。
そんなときは、「う」のつく食べ物をうまく活用して、子どもが喜んで食べられるメニューにアレンジしてみましょう。
以下は、栄養バランスと食べやすさを兼ね備えた、“子ども向け”のおすすめ食材です。
● うどん(アレンジ次第でバリエーション豊富!)
細めでツルっとした食感が魅力のうどんは、離乳食を卒業したばかりの小さなお子さまから、食欲が落ちがちな暑い日にもぴったりです。冷やしうどんにツナや温泉卵、コーンをトッピングすれば、見た目も楽しく栄養もアップ!
● うずらの卵(見た目もかわいく、タンパク源にも)
小さくてコロンとしたうずらの卵は、ゆでてお弁当のおかずにしたり、カレーやシチューに入れると子どもにも大人気。鉄分やビタミンB群など、成長期に必要な栄養素も含まれています。
● うめゼリー(クエン酸で疲労回復&夏らしいデザート)
梅干しは酸味が苦手なお子さまもいますが、ゼリーに加工した「うめゼリー」なら食べやすくなります。市販でも販売されていますし、自宅で手作りする際はハチミツなどでやさしい甘さに調整すると◎。
● うに風味のふりかけ(プチ贅沢&ごはんが進む!)
本物のうには子どもには少し大人の味ですが、うに風味のふりかけなら手軽に“う”の食材を楽しめます。ごはんにふりかけておにぎりにするのもおすすめです。
こうした工夫を取り入れることで、子どもたちも「う」のつく食べ物を楽しみながら、季節の変わり目を元気に乗り越えることができます。ご家族で「今日は“う”の日だよ!」と声をかけながら食卓を囲む時間も、きっと心に残る夏の思い出になるでしょう。
うなぎが高くなった背景には、深刻な資源問題がある

一昔前までは、うなぎは庶民にとっても手の届く食材でした。しかし近年では、価格が上昇し、「高級品」という印象が強まっています。
その理由のひとつが、天然うなぎの激減と、それに伴う資源保護の必要性です。
特に日本国内で食べられている「ニホンウナギ」は、2014年に環境省から絶滅危惧種に指定されました。これは、世界的にも深刻な問題とされており、国際的な保護対象にもなっています。
現在流通しているうなぎの多くは養殖ですが、その養殖もうなぎの稚魚である「シラスウナギ」の捕獲に依存しています。
つまり、「養殖だから安心」とは言いきれず、うなぎそのものの存続が危ぶまれている状況に変わりはないのです。
私たちにできる小さな選択が、うなぎの未来を守る力に

こうした背景を踏まえると、私たち消費者も“うなぎとの付き合い方”を見直すことが求められています。具体的には、次のような意識を持つことが大切です。
- 必要以上に購入せず、大切に味わう
- うなぎを提供しているお店やメーカーの、資源保護への取り組みを確認する
- うなぎ以外の食材も積極的に取り入れ、選択肢の幅を広げる
これらは一人ひとりが今すぐにでもできる、小さな行動です。しかし、それが積み重なることで、持続可能な消費や環境への配慮につながっていきます。
まとめ|「土用の丑の日」の本質を、今年は味わってみませんか?
「土用の丑の日」と聞くと、どうしても“うなぎを食べる日”というイメージばかりが先行しがちです。
でもその奥には、古代の自然観や陰陽五行、干支といった思想、そして人々の暮らしの知恵が脈々と息づいていることをご存じでしょうか?
民間信仰、暦、そして商人たちの工夫――さまざまな要素が時代を越えて積み重なり、今の私たちの生活にこの風習が残っているのです。
2025年は「一の丑」と「二の丑」が訪れる特別な年。うなぎにこだわらず、「う」のつく食べ物や旬の野菜を食卓に取り入れながら、自分の体を気遣うきっかけにしてみてください。
ただの年中行事としてではなく、その背景にある意味を知り、丁寧に味わうことで、きっと「土用の丑の日」は、あなたにとってもっと価値のある1日になるはずです。