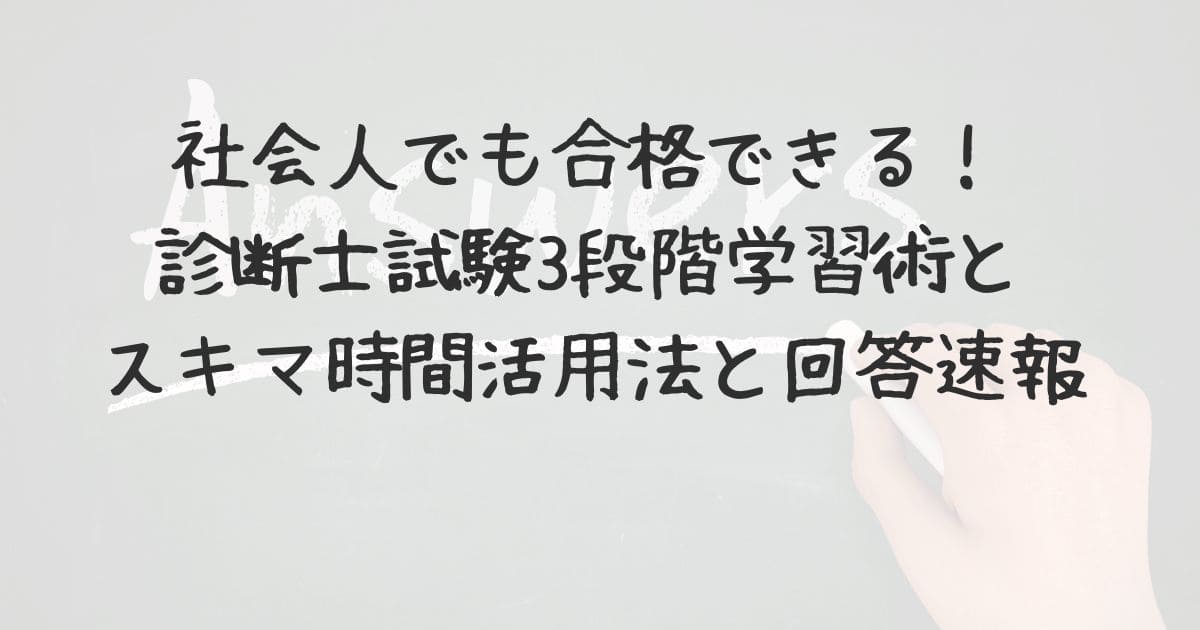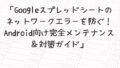- 資格の位置づけと魅力
- 取得するメリットは「汎用性」と「信頼性」
- 2025年度 解答速報を素早く入手するには?
- コミュニティ発信型の速報ルートも活用
- 年間スケジュールと試験全体の流れ
- 一次試験(多肢選択式・7科目)
- 二次試験(事例演習形式)
- 実務補習・実務従事
- 合格率の最新データから見える試験の実態
- 難易度を数値と比較して理解する
- 受験生がつまずくポイントをデータで分析
- 社会人合格者のリアルな時間割
- 数字が示す“挫折ライン”と突破口
- 学習全体の戦略:3段階のフェーズで効率化
- インプット期:教材とスキマ時間の徹底活用
- 演習期:アウトプット重視の学習計画
- 直前30日間の“スパート”学習メニュー
- モチベーションを維持する方法と学習コミュニティの活用
- まとめと次の一歩
資格の位置づけと魅力

経営コンサルタント分野で唯一の国家資格
中小企業診断士は、日本国内で 唯一、経営コンサルタントとして公式に認められた国家資格です。
資格を保有していることで、企業経営に関する高度な知識と診断スキルを有していることが証明されます。
経営の現場ではもちろん、個人のキャリアアップやコンサルタントとしての独立開業にも大きな力を発揮します。
活躍の場は「中小企業」にとどまらない
名称に「中小企業」と含まれていますが、その適用範囲は幅広く、大企業やベンチャー企業、地方自治体の政策立案など多様な分野で活かすことが可能です。
経営改善や事業再生、組織改革、さらには地域振興策など、多様なシーンで専門性が求められます。
取得するメリットは「汎用性」と「信頼性」

経営全般を横断する知識が身につく
中小企業診断士試験の一次試験では、経済学、財務・会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、情報システム、中小企業政策といった 7科目 を学びます。
これにより、経営を多角的に理解するフレームワークが養われ、マネジメントスキルを体系的に習得できる点が大きな魅力です。
実務補習で現場経験を積める
試験に合格すると、3年以内に 15日以上 の実務補習または実務従事を行う必要があります。
この実務補習では、実際の企業に訪問し、経営診断や改善提案をまとめる経験を積むことが可能です。
机上の学びを現場で試せるため、資格取得後のスキルとしてすぐに活かせます。
2025年度 解答速報を素早く入手するには?

主要スクールの公式速報をチェック
試験終了後、複数の予備校が解答速報を公開します。
速報のスピードや付加サービスに特徴があるため、複数の情報源を確認すると良いでしょう。
※「資格の大原」や「LEC東京リーガルマインド」は、2025年度の解答速報は公表しない予定です(7月時点の情報)。
コミュニティ発信型の速報ルートも活用

X(旧Twitter)
SNSでは、#中小企業診断士試験解答速報 のハッシュタグを中心に受験生が自己採点結果や速報情報を投稿しています。
リアルタイムで情報が流れるため、試験直後から活発な情報交換が期待できます。
5ch 受験生スレ
匿名掲示板5chでは、受験生たちがスクールごとの解答PDFを比較し、誤りを修正しながら精度の高い速報をまとめています。
毎年、完成度の高い最終版がいち早く共有されるため、多くの受験生が参考にしています。
ワンポイントアドバイス
解答速報のPDFは頻繁に更新されるため、確認する際は必ず 最新版にリロード してから内容をチェックしましょう。早期情報をもとに自己採点すれば、二次試験への準備をすぐに始められます。
年間スケジュールと試験全体の流れ

中小企業診断士試験は、一次・二次(筆記・口述)そして実務補習を経て正式登録に至る流れで進行します。
ここでは、令和7年度(2025年度)に基づいたスケジュールと各試験のポイントを詳しく説明します。
一次試験
例年、8月上旬の土日2日間にわたって実施されます。
合格発表は9月上旬に行われ、ここを突破した受験者のみが二次試験に進むことができます。
二次筆記試験
一次合格者は、10月第3日曜日に行われる二次筆記試験に挑みます。
試験は1日で完結し、結果は12月中旬に公表されます。
二次口述試験
筆記試験合格者のみが受験可能で、翌年1月中旬に実施されます。
個人面接形式で約10分間行われ、1週間後に最終合格者が発表されます。
登録要件(実務補習/実務従事)
二次試験合格後、3年以内に通算15日以上の実務補習または実務従事を経験し、診断報告書を提出すると登録が可能になります。
一次試験(多肢選択式・7科目)

科目構成と試験時間
一次試験は7科目で構成され、それぞれ100点満点です。
| 科目名 | 配点 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 経済学・経済政策 | 100点 | 60分 |
| 財務・会計 | 100点 | 60分 |
| 企業経営理論 | 100点 | 90分 |
| 運営管理(オペレーションマネジメント) | 100点 | 90分 |
| 経営法務 | 100点 | 60分 |
| 経営情報システム | 100点 | 60分 |
| 中小企業経営・政策 | 100点 | 60分 |
※試験内容および時間割は令和7年度試験案内に基づきます。
合格判定ルール
-
総得点 420点以上/700点満点(60%)
-
1科目でも40点未満があると不合格
-
科目合格制度あり:60%以上の得点を取った科目は翌2年間免除されます
戦略メモ:苦手科目がある場合は、科目合格を活用し計画的に合格を目指す“分割突破”が可能です。
二次試験(事例演習形式)

筆記試験(4事例)
二次筆記は4つの事例を通じて、与えられた企業課題に対して具体的な助言を記述する形式です。
| 事例 | 主題 | 出題の狙い |
|---|---|---|
| Ⅰ | 組織・人事 | 組織構造や人材マネジメントの改善策を提案 |
| Ⅱ | マーケティング・流通 | 顧客価値向上と売上拡大施策を設計 |
| Ⅲ | 生産・技術 | 生産現場の効率化と品質管理を診断 |
| Ⅳ | 財務・会計 | 財務分析と数値を使った課題解決を提示 |
合格基準
-
総得点 240点以上/400点満点(60%)
-
各事例で40点未満がないこと
-
科目合格制度はなし
口述試験
口述は、筆記試験で出題された事例を基に面接官の質問に答える形式です。
所要時間は約10分で、質問はランダムに出されます。
合格率は99%以上と非常に高く、基本的に筆記試験を突破していれば問題なく通過できる内容です。
注意点:口述試験は「知識を確認する場」。重大な失態がなければ落とされることはほとんどありません。
実務補習・実務従事

実務補習(協会実施)
中小企業診断協会が主催し、5日間×3クール=計15日で構成されます。
チームで企業を訪問し、診断や助言をまとめる実践的プログラムです。
実務従事(自己開拓)
自ら案件を探して企業診断を行い、報告書を提出することで日数換算されます。
自治体のプロジェクトなども対象となります。
ポイント:どちらの方法でも、合計15日を満たせば登録要件をクリアできます。
2025年度 最新情報と注意点
-
合格基準は現行ルール(総得点60%+各科目40%)が継続されます
-
受験料は一次試験14,500円、二次試験17,800円に据え置き
-
試験案内は紙冊子が廃止され、ウェブ配布のみ
-
申込もオンライン限定となり、マイページの作成と締切管理が必須
重要:科目免除申請や受験地変更は受付期間内のみ可能です。早めに準備を進め、スケジュールをしっかり把握しましょう。
合格率の最新データから見える試験の実態

一次試験:年度ごとの変動に注目
一次試験の合格率は毎年大きく変動します。
2024年度(令和6年)は27.5%と、過去10年間の平均をやや上回る水準でした。
特に「経営情報システム」は変動幅が大きく、2021年は10.6%、2022年は18.5%、2023年は11.4%と乱高下が続いています。
このため、年度ごとの難易度変化を踏まえた戦略が必要です。
二次筆記:例年ほぼ横ばいの18%前後
二次筆記試験は、一次を突破した受験者が集まるため競争が激化します。
2024年度の合格率は18.7%で、合格者数は1,516人でした。2015年以降、10年連続で18〜19%付近を維持しており、安定した難易度が特徴です。
最終合格率:厳しさを物語る5%前後
一次と二次の結果を掛け合わせると、最終合格率は5.14%(2024年度)にとどまります。
長期的に見ても、4〜8%の範囲から外れた年度はなく、受験者が二段階でふるい落とされる試験構造が、この資格の難しさを際立たせています。
難易度を数値と比較して理解する
学習時間は1,000時間が目安
TACやアガルートでは、合格までに必要な学習時間は約1,000時間とされています。
1年計画の場合は平日2時間、土日5時間を継続するペース。2年計画なら週10時間でも達成可能です。
偏差値で例えると「MARCHレベル」
大学入試の偏差値で表すと、中小企業診断士の難易度は偏差値62程度、上位約12%に入る水準とされています。
数値だけ見ても、容易ではないことが分かります。
「やめとけ」と言われる理由
診断士は独占業務がないため、資格取得がそのまま収入保証につながるわけではありません。
また、AIの進化により一部の業務が自動化される可能性も指摘されています。
ただし、企業内での昇進や副業コンサルとしての活用など、他のスキルとの掛け算で価値を高めやすい資格でもあります。
受験生がつまずくポイントをデータで分析
一次試験の鬼門科目
過去10年間の統計によれば、特に合格率が低いのは経営情報システムと経営法務です。
これらは用語暗記が多く、難解な出題も多いため、過去問演習を繰り返し、スキマ時間で用語を徹底暗記する学習法が効果的です。
二次試験・事例Ⅳ(財務)での大きな壁
二次試験では、事例Ⅳ(財務・会計)が多くの受験生を苦しめています。
合格ラインの60点を突破するには、計算問題を正確に解答する力が必須。克服には、財務三表の素早い読解やCVP分析・NPV計算などの型を反復練習することが重要です。
社会人合格者のリアルな時間割
| 勉強フェーズ | 平日 | 休日 | 工夫 |
|---|---|---|---|
| インプット期 | 通勤往復60分 | 午前3時間 | スマホ講義+耳学習 |
| 演習期 | 仕事後90分 | 午前・午後で5時間 | WEB模試+答案添削 |
| 直前期 | 早朝30分 | 模試+復習6時間 | 過去問3回転 |
ある受験生は「平日は1時間でも継続し、休日に学習時間を増やす」戦略で1年で一発合格を達成しました。
また、海外勤務中の受験生も、スタディングなどオンライン講座を活用し3年でストレート合格を果たすなど、状況に応じた学習方法が成功につながっています。
数字が示す“挫折ライン”と突破口
-
一次試験平均点が420点未満の年は、救済措置として難易度調整が行われることがあります。
-
二次試験の得点開示では、事例Ⅳで30点台を取った受験生が不合格者の大半を占める傾向があります。
-
2〜3月はモチベーションが下がりやすく、挫折する人が最も多い時期です。
打開策
-
学習計画を3週間単位に区切り、小さな達成感を積み重ねる
-
SNSで学習進捗を発信し、外部から刺激を受ける
-
**財務対策は「計算問題100本ノック」**で手を動かし、体で覚える
これらのデータと対策を活かせば、難関と言われる中小企業診断士試験も現実的に攻略可能です。
大切なのは、数字に怯まず、自分なりの戦略を継続して実行することです。
学習全体の戦略:3段階のフェーズで効率化

中小企業診断士試験を突破するためには、学習を3つのフェーズに分けて計画的に進めることが重要です。
合格者の平均学習時間は一次・二次を合わせて約1,000時間。この時間を無理なく確保するため、各フェーズでの学習比率とゴールを明確にします。
| フェーズ | 学習比率 | 期間の目安 | 主なゴール |
|---|---|---|---|
| インプット期 | 60% | 試験12〜6か月前 | 7科目の基礎知識を体系的に習得 |
| 演習期 | 30% | 試験6〜2か月前 | 過去問5年分を2周+模試で実戦力を養成 |
| 直前期 | 10% | 試験30日前〜当日 | 弱点分野の克服と時間配分の最適化 |
インプット期:教材とスキマ時間の徹底活用

おすすめ教材・オンライン講座
-
スタディング総合コース
スマホ1台で完結でき、動画学習とAI復習機能が充実。移動時間にも学習可能。 -
TAC基本テキスト+速習メソッド
出題範囲を広くカバーし、図解を多用して理解しやすい構成。 -
暗記カードアプリ(例:WordHolic)
自作カードや市販データを利用し、重要用語を短時間で反復記憶。
スキマ時間活用のコツ
-
通勤時間の活用:講義音声を倍速再生し、往復60分をインプットに充てる。
-
昼休み10分の集中暗記:暗記カードを使い、週5日で合計50分の知識強化。
日々の隙間を積み上げることで、年間240時間以上の学習時間を自然に確保できます。
演習期:アウトプット重視の学習計画
過去問+模試のルーティン
演習期は、知識を使える形にする段階です。過去問と模試を組み合わせ、弱点を逐次修正します。
| 週 | 平日(60分) | 土日(各150分) |
|---|---|---|
| 1週目 | 過去問1科目 | TAC公開模試の復習 |
| 2週目 | 過去問1科目 | LEC全国模試(科目別) |
| 3週目 | 過去問1科目 | 自己採点→弱点ノート更新 |
| 4週目 | 総復習 | ミニテスト(自作30問) |
二次試験対策の必須ツール
-
ふぞろいな合格答案シリーズ:先輩合格者の答案を基に採点基準を理解。
-
事例Ⅳ 100本ノック:財務計算を繰り返し、数値問題に対する反射力を養成。
直前30日間の“スパート”学習メニュー

直前期は得点を伸ばす最後のチャンスです。以下のように日数ごとに計画を立てると効果的です。
| 日数 | 一次対策 | 二次対策 | 目的 |
|---|---|---|---|
| D-30〜D-21 | 法務・情報システムの暗記総仕上げ | 事例Ⅰ〜Ⅲの骨子作成 | 知識呼び戻し |
| D-20〜D-11 | 財務過去問3年分を時間制限付きで演習 | 事例Ⅳ計算ドリルを毎日1セット | 解答速度UP |
| D-10〜D-4 | 全科目のファイナルペーパー作成 | 筆記答案40字要約×20問 | 記述精度UP |
| D-3〜D-1 | 模試復習ノートを総仕上げ | 口述試験想定Q&Aを30題確認 | メンタル調整 |
| 試験当日 | 早朝に暗記事項を確認 | 事例Ⅳ公式の最終確認 | ルーティン固定 |
アドバイス:財務は「公式を忘れた瞬間に失点」するため、ファイナルペーパーを持ち歩くと安心です。
モチベーションを維持する方法と学習コミュニティの活用

-
SNSで学習を宣言:X(旧Twitter)で「#診断士勉強仲間」と投稿し、仲間と進捗共有。
-
オンライン自習室の活用:スタディングの“もくもく会”に週1回参加し、学習リズムを維持。
-
合格体験記を読む:成功者のストーリーから刺激を受け、学習モチベーションを高める。
受験生の多くは2〜3月にやる気が落ち込みます。外部刺激を受けられる環境を先に作っておくと、挫折を防止できます。
まとめと次の一歩
-
学習戦略はフェーズ×教材の組み合わせで明確化し、優先すべきタスクを把握する
-
年間240時間のスキマ学習を積み重ねれば、1,000時間の目標も無理なく達成可能
-
直前30日は苦手科目の点数底上げと事例Ⅳの計算精度強化に一点集中
-
学習ログを公開し、モチベーションを外部化することで最後まで走り切れる
この計画を実行すれば、難関と言われる中小企業診断士試験も着実に合格へ近づくことができます。